この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。
ヘルニアによる痛みやしびれに悩まされていませんか?多くの方が「温めるべきか、冷やすべきか」と迷われます。結論からいうと、ヘルニアの場合、痛みが強い初期には患部を冷やし、炎症を抑えるのが基本です。症状が改善し、痛みが落ち着いてきたら、温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげるのも効果的です。
この記事では、ヘルニアの症状別・時期別の正しい温熱療法と冷却療法の選び方、具体的な方法、そして専門家の見解をご紹介します。ヘルニアの痛みを効果的に緩和し、日常生活への復帰を早めるための正しい知識を身につけましょう。
ヘルニアの急性期には冷やすことが基本です。炎症が起きていると、その部分に熱がこもり余計に痛みが増していきます。まずは患部の熱を取り除くことが大切です。
目次
ヘルニアとは?炎症と痛みのメカニズム

ヘルニアとは、椎間板の中心部分(髄核)が外側に飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす状態です。主に腰椎椎間板ヘルニアと頚椎ヘルニアがあり、特に腰椎ヘルニアは腰痛や坐骨神経痛の主な原因となります。
ヘルニアの主な症状
ヘルニアになると、以下のような症状が現れることが多いです:
- 腰の痛み・重い感じ
- 足のしびれや痺れ(坐骨神経痛)
- 神経が圧迫される感覚
- 長時間同じ姿勢を続けると痛みが増す
- 咳やくしゃみで痛みが強くなる
なぜ炎症が起きるのか?
ヘルニアでは、飛び出した髄核が周囲の組織や神経を刺激することで炎症反応が起こります。炎症には熱感、腫れ、痛みなどの症状が伴い、これが患部の熱を生み出す原因になります。この炎症状態をどう扱うかが、温めるか冷やすかの判断の重要なポイントになります。
ヘルニアは温めるべき?冷やすべき?判断のポイント

症状の時期(急性期か慢性期か)と炎症の有無によって、ヘルニアを温めるか冷やすかを判断しましょう。以下の基準を参考にしてヘルニアの温め方と冷やし方を選択してください。
| 状態 | 推奨される対処法 | 理由 |
|---|---|---|
| 急性期(発症から72時間以内) ・強い痛みがある ・熱感がある ・炎症症状が明らか | 冷やす | 炎症を抑え、痛みを和らげる 血管を収縮させ、腫れを軽減する |
| 慢性期(急性期を過ぎた後) ・痛みが落ち着いてきた ・炎症症状が軽減した ・筋肉の緊張が主な原因 | 温める | 血行を促進し、栄養を届ける 筋肉の緊張をほぐす 組織の柔軟性を高める |
| 慢性的な腰痛で炎症がない場合 | 温める | 血流改善による痛みの緩和 筋肉のこわばりを取り除く |
| 運動後の予防的ケア | 冷やす → 温める | まず炎症を予防し、その後筋肉をリラックスさせる |
症状の判断が難しい場合は?
もし「急性期か慢性期か」「炎症があるのかないのか」の判断が難しい場合は、以下の基準を参考にしてください:
- 痛みが強く、安静にしていても痛む → 冷やすことを試してみる
- 患部に触れると熱感がある → 冷やす
- 動き始めの痛みが主で、動くと徐々に楽になる → 温めることを試してみる
- 寒くなると痛みが増す → 温める
どちらの方法を試しても痛みが悪化する場合は、すぐに中止し、医療機関での診察を受けることをおすすめします。
【冷やすケース】効果と正しいアイシング方法

冷やすことの効果
ヘルニアの急性期に冷やすことには、以下のような効果が期待できる可能性があります
- 炎症反応の抑制
- 血管の収縮による腫れの軽減
- 神経の興奮を鎮め、痛みを和らげる
- 組織の代謝を遅らせ、炎症物質の産生を抑える
正しい冷やし方(アイシング方法)
効果的に冷やすためには、正しい方法で行うことが重要です:
- 準備するもの: 氷嚢や保冷剤、タオル
- 冷やす時間: 1回につき10~20分程度
- 冷やす頻度: 症状が出始めてから最初の3日間は、1~2時間おきに繰り返す
- 保護方法: 凍傷を防ぐため、氷嚢や保冷剤を直接肌に当てず、タオルで包んでから使用する
- 冷やす強さ: 「気持ち良い冷たさ」を感じる程度に調整する
冷やす際の注意点
以下の点に注意して冷やすことで、より効果的かつ安全にケアできます:
- 冷やしすぎると血流が悪くなりすぎて回復を遅らせることがあるため、20分以上の長時間冷やし続けないこと
- 皮膚が敏感な方は、タオルを厚めに巻いて調整する
- 冷やしている間に痛みが増したり、しびれが強くなったりした場合はすぐに中止する
- 心臓病や循環器系の疾患、感覚障害のある方は医師に相談してから行う
【温めるケース】効果と正しい温め方
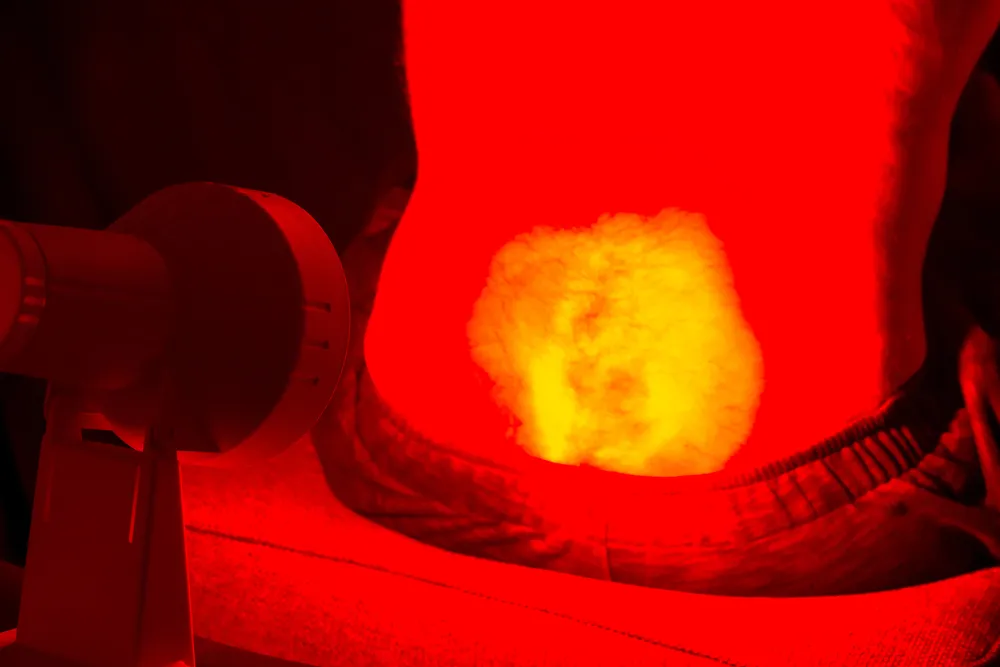
温めることの効果
ヘルニアの慢性期や炎症が落ち着いた段階で温めることには、以下のような効果が期待できる可能性があります:
- 血行促進による栄養供給の増加
- 筋肉の緊張緩和
- 組織の柔軟性向上
- 痛みの緩和
- 動きやすさの改善
正しい温め方
効果的に温めるためには、以下の方法が推奨されます:
- 準備するもの: 温湿布、カイロ、温タオルなど
- 温める時間: 1回につき15~20分程度
- 温める頻度: 1日2~3回
- 適切な温度: 低温やけどを避けるため、熱すぎない程度(40~42度程度)に調整する
温める際の注意点
温める際は以下の点に注意しましょう:
- 急性期(症状が出始めてから72時間以内)は温めないこと
- 炎症がある場合は温めると症状が悪化する可能性があると考えられています
- 温めすぎると皮膚の炎症や低温やけどを起こす恐れがあるため、適度な温度に保つ
- 就寝中など長時間の使用は避ける
- 温めた後に痛みが増したり、症状が悪化したりした場合はすぐに中止する
ヘルニアの時にやってはいけないこと

ヘルニアの症状を悪化させないために、以下のような行動は避けるべきです:
急性期にやってはいけないこと
- 患部を温めること: 炎症を悪化させる可能性がある
- 激しい運動や負担のかかる動き: 症状を悪化させる
- 長時間の同じ姿勢: 特に前かがみの姿勢は椎間板への負担が大きい
- 重いものを持つこと: 腰への負担が増加する
- 症状があるのに我慢して活動を続けること: 炎症を悪化させる
慢性期に注意すべきこと
- 過度な安静: 筋力低下を招き、回復を遅らせる可能性がある
- 適切なケアなしでのスポーツ復帰: 再発のリスクが高まる
- 姿勢の悪さを放置すること: 椎間板への不均等な圧力がかかる
- 腹筋や背筋の筋力低下: 腰椎の安定性が失われる
症状別の対処法

急性期の強い痛みがある場合
発症直後や痛みが強い急性期には、以下の対処を行いましょう:
- 安静にする: 特に最初の24~72時間は安静が重要
- 冷やす: 1~2時間おきに10~20分程度のアイシング
- 痛みのない姿勢を見つける: 横向きに寝て膝を軽く曲げる姿勢が良いことが多い
- 適切な姿勢を保つ: 腰をサポートするクッションやコルセットを活用
- 医療機関の受診: 痛みが強い場合は早めに受診する
炎症が落ち着いた慢性期の場合
炎症が落ち着き、急性期を過ぎた段階では:
- 温める: 血流改善と筋肉の緊張緩和のために温める
- 軽いストレッチと適度な運動: 筋力維持と血行促進のため
- 正しい姿勢の維持: 日常生活での姿勢に注意する
- 定期的な休息: 同じ姿勢が長時間続かないようにする
- 体重管理: 腰への負担を減らすために適正体重を維持する
坐骨神経痛を伴う場合
足にしびれや痛みが放散する坐骨神経痛の症状がある場合:
- 神経の通り道を圧迫しない姿勢を取る
- 急性期は冷やす: 特に痛みの強い部分をアイシングする
- 慢性期は温める: 筋肉の緊張を和らげる
- 神経の滑走性を改善するストレッチ: 医師や理学療法士の指導のもとで行う
自宅でできるセルフケア

専門家による治療と並行して、自宅でも以下のようなセルフケアを行うことで症状の改善を促進できる可能性があります:
日常生活での姿勢管理
- 座る時の姿勢: 腰が丸まらないよう、背もたれにしっかり寄りかかる
- 立つ時の姿勢: 片足に体重をかけず、両足に均等に分散させる
- 寝る時の姿勢: 仰向けで膝の下にクッションを置く、または横向きで膝を軽く曲げる
- 長時間同じ姿勢を避ける: 30分ごとに姿勢を変える、または軽く体を動かす
安全なストレッチ(医師に相談してから)
医師や理学療法士に確認してから、以下のようなストレッチを行うと効果的と考えられています:
- 膝抱え運動: 仰向けに寝て、片膝ずつ胸に向かって軽く引き寄せる
- 骨盤傾斜運動: 仰向けに寝て、骨盤を前後に傾ける
- 猫のポーズ: 四つん這いになり、背中を丸めたり反らしたりする
※ストレッチは痛みが出ない範囲で行い、痛みを感じたらすぐに中止してください。
生活習慣の改善
- 適正体重の維持: 腰への負担を減らす
- 喫煙の回避: 血流を悪化させ、椎間板の栄養供給を妨げる
- 水分摂取: 椎間板の水分保持を助ける
- 腹筋・背筋の強化: 腰のサポート力を高める(医師の許可を得てから)
専門家に相談するタイミング

以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう:
- 安静にしていても強い痛みがある
- 足の痺れや筋力低下が進行している
- 排尿や排便に問題が生じた
- 発熱を伴う腰痛がある
- 転倒や事故の後に腰痛が生じた
- 3週間以上症状が改善しない
どのような医療機関を受診するべきか
- 整形外科: 診断と薬物療法、注射、手術適応の判断など
- ペインクリニック: 痛みの管理(ブロック注射など)
- 理学療法科: リハビリテーション
- 整骨院・鍼灸院: 補完的な治療(医師の診断後に)
受診する際は、症状の発症時期や変化、どのような時に痛みが強くなるかなど、詳しい情報を伝えるようにしましょう。
まとめ:ヘルニアの温め・冷やしの基本原則

ヘルニアの痛みに対する温熱療法と冷却療法の選択は、症状の時期や状態によって大きく異なります。以下が基本的な原則です:
- 急性期(発症から72時間以内): 冷やす – 炎症を抑え、痛みを和らげる
- 慢性期(炎症が落ち着いた後): 温める – 血行を促進し、筋肉の緊張を緩和する
- 症状が悪化する場合: すぐに医療機関を受診する
- 自己判断が難しい場合: 専門家に相談する
ヘルニアは適切なケアと生活習慣の改善によって、多くの場合症状を緩和できる可能性があるとされています。正しい知識を身につけ、自分の状態に合った対処法を選択することで、痛みのない快適な生活を取り戻しましょう。今日から正しいケアを始めて、ヘルニアの痛みから解放されましょう!
ヘルニアの温め方・冷やし方に関するよくある質問

Q. ヘルニアの場合、温めると痛みが悪化することがあるのはなぜですか?
A. ヘルニアの急性期には炎症が起きており、その部分にはすでに熱がこもっています。この状態で温めると、炎症反応がさらに活発になり、腫れや痛みが増加する可能性があります。また、温めることで血流が増加し、炎症部位の腫れが悪化することもあります。そのため、急性期(特に最初の72時間)は温めずに冷やすことが推奨されています。
Q. ヘルニアの初期に冷やす場合、何日くらい続けるべきですか?
A. 一般的に、症状が出始めてから最初の3日間(72時間)は冷やすことが推奨されています。この期間は炎症反応が最も活発な時期と考えられています。3日経過後も強い痛みや熱感が続く場合は、さらに冷やし続けることもありますが、症状が和らいできたら温熱療法に切り替えることを検討しましょう。判断に迷う場合は、医師や理学療法士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q. 温めると気持ちいいと感じる場合でも、急性期なら冷やすべきですか?
A. はい、急性期(発症から72時間以内)は、温めると気持ちよく感じたとしても、基本的には冷やすことが推奨されます。温めると一時的に気持ちよく感じることがありますが、炎症を悪化させる可能性があると考えられています。炎症が強まると、その後さらに痛みが増す恐れがあります。特に熱感や強い痛みがある場合は、気持ちよさよりも医学的な原則に従って冷やすことを優先しましょう。
Q. 慢性的な腰痛とヘルニアの痛みを見分ける方法はありますか?
A. 慢性的な腰痛とヘルニアの痛みは、症状の現れ方に違いがあります。ヘルニアの場合は、腰痛に加えて足へのしびれや痛みが放散することが多く、特定の姿勢(前かがみなど)で痛みが悪化する傾向があります。また、咳やくしゃみで痛みが増すこともヘルニアの特徴です。一方、単純な筋肉性の慢性腰痛は、主に腰部に限局し、動作による痛みの変化が少ないことがあります。正確な判断には医師による診察が必要です。
Q. 冷やす時と温める時の具体的な目安の時間はどれくらいですか?
A. 冷やす場合は、1回につき10~20分程度が目安です。急性期(最初の72時間)は1~2時間おきにこの時間冷やすと効果的と考えられています。20分以上の長時間冷やし続けると、逆に血流が悪くなりすぎて回復を遅らせる可能性があります。一方、温める場合は、15~20分程度を1日に2~3回行うのが適切とされています。どちらの場合も、不快感を感じたらすぐに中止してください。また、就寝中など長時間の使用は避けましょう。
Q. ヘルニアの痛みがある時にお風呂に入っても大丈夫ですか?
A. 急性期(発症から72時間以内)は、お風呂でからだ全体を温めることで、炎症部位の血流が増加し、症状が悪化する可能性があるため、シャワーで体を清潔に保つ程度にとどめることをおすすめします。急性期を過ぎ、炎症が落ち着いてきたら、ぬるめのお風呂(38~40度程度)に短時間(10~15分程度)入ることで、筋肉の緊張緩和や血行促進の効果が期待できる可能性があります。ただし、熱いお風呂や長湯は避け、入浴後に症状が悪化する場合はすぐに医師に相談してください。
Q. 市販の温湿布と冷湿布はどのように使い分ければよいですか?
A. 市販の温湿布と冷湿布は、ヘルニアの症状の時期に合わせて使い分けます。急性期(発症から72時間以内)で炎症症状が強い時は冷湿布を使用し、炎症を抑え、痛みを和らげられる可能性があります。急性期を過ぎ、炎症が落ち着いてきたら温湿布に切り替え、血行を促進し、筋肉の緊張を緩和する効果を得ることができると考えられています。どちらを使用する場合も、指示された使用時間を守り、就寝中など長時間の連続使用は避けてください。また、温湿布で痛みが増す場合は使用を中止し、冷湿布に戻すか医師に相談しましょう。

