肩こりは現代人の多くが悩まされている症状の一つです。デスクワークが増え、スマホを見る時間が長くなった現代社会では、姿勢の悪さやストレスなどが原因で肩こりを抱える人が増えています。「肩が凝っているね」と言われても、自分では肩こりかどうかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、肩こりを自分で触って確認する方法や、痛みのポイント、そして効果的な改善策について詳しく解説します。
目次
肩こりとは?その正体と原因を知ろう

肩こりは、首から肩、背中にかけての筋肉の緊張や血行不良によって引き起こされる不快な症状です。首のつけ根から肩または背中にかけての痛みや重だるさ、張り感があり、それを自身が不快に感じれば肩こりと言えます。日本人の国民病とも言われ、過去50年間にわたって上位を占める一般的な症状となっています。
肩こりの範囲は実は広く、次の2種類に大別できます:
- 首の神経から起こる肩こり:後頭部、耳周辺、首、肩、腕まで症状が広がる
- 肩から起こる肩こり:肩関節周辺に痛みや違和感がある
肩こりの原因は大きく3つに分類される
- 本態性肩こり
- 過労や疲労
- 運動不足
- 冷え
- 悪い姿勢
これらは生活習慣の改善や適切な体のケアで解消できる可能性が高いです。
- 症候性肩こり
- 変形性頚椎症
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 四十肩・五十肩
- 高血圧や心臓病などの内科的疾患
これらは病気が原因で起こる肩こりで、専門医の診察が必要な場合があります。
- 心因性肩こり
- うつ病
- 不安障害
- 強いストレス
精神的な要因から肩こりが発生するケースです。
肩こりは触ってわかる?痛みのポイントとセルフチェック方法
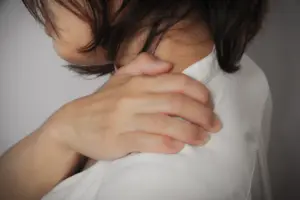
多くの人が「肩こり」と聞くと、ゴリゴリとした硬いしこりを想像するでしょう。実際、肩こりがある場合は筋肉が緊張して硬くなっている場合が多いですが、必ずしも肩の硬さだけで判断できるわけではありません。
肩が硬くても肩こりの痛みを感じていない人もいれば、触った感じは特に変わらなくても強い肩こりに悩まされている人もいます。肩こりの定義は「本人が不快に感じる首・肩・背中の痛みや張り、重だるさ」であり、自覚症状が重要です。
自分でできる肩こりセルフチェック9つのポイント
肩こりかどうかを自分で確認するには、以下の場所を軽く押してみて、痛みや違和感があるかチェックしましょう。
- 胸鎖乳突筋:耳の後ろから鎖骨前部につながる筋肉を押す。痛みがあれば肩こりの可能性大。
- 後頭部(大後頭神経):頭の付け根にある「天柱」というツボを押す。ここは首の神経が頭に入る重要なポイントで、押したときに痛みがあると肩こりが疑われる。
- 首筋の筋肉:首の後ろ側を触って硬さや痛みをチェック。特に耳の後ろから鎖骨にかけての筋肉が硬い場合は注意が必要。
- 僧帽筋:首から肩、背中にかけて広がる筋肉で、肩こりの方は特にここが硬くなりやすい。触って痛みがあれば肩こりのサイン。
- 肩甲骨の間:背中の中央部分を押して痛みをチェック。
- 肩甲骨の上部:肩甲骨と首の間を押す。ここは肩こりがある方によく痛みが出るポイント。
- 肩甲骨の下部:肩甲骨の下側を押して痛みをチェック。
- 腕の外側:「手三里」というツボ(肘の曲げ目から指3本分下の外側)を押す。肩こりの程度を知るのに有効。
- 首の付け根:首と肩が接する部分を押して確認。この部分は特に肩こりが出やすい場所。
これらの場所を押して痛みを感じる場合は、肩こりの可能性があります。特に、複数の場所で痛みがあれば、肩こりである可能性が高まります。自分で触って痛みを感じるポイントが多ければ多いほど、肩こりの症状が進行している可能性があります。
動きでチェックする方法
体の動きで肩こりを自分で確認する方法もあります:
- 肩回しセルフチェック:腕を固定して肩だけを大きく前後に回します。肩こりがある場合、スムーズに動かせない、どこかで痛みや抵抗を感じる場合があります。
- バンザイポーズ:両手を上に挙げて鏡で確認します。左右の高さが違う、挙げるのがつらい場合は肩こりのサインかもしれません。
- 体の歪みチェック:鏡の前で姿勢を確認し、肩の高さに左右差がないか見ます。歪みがある場合は、無意識のうちに肩こりが発生している可能性があります。
肩こりの「コリ」の正体は筋肉?筋膜?触るとゴリゴリの原因

超音波エコーで肩こりの部位を観察すると、筋肉だけでなく、筋膜にも変化が見られることがわかっています。触ったときのゴリゴリした感触の正体は、筋膜のシワや癒着であることが多いのです。
筋膜とは?
筋膜とは、筋肉を包み込む薄い膜で、「第二の骨格」とも呼ばれる重要な組織です。コラーゲンやエラスチンといった成分からできており、弾力性がありながらもしなやかさを持っています。筋膜は全身にわたって張り巡らされており、まるで体を覆うボディスーツのように働きます。この筋膜がねじれたり癒着したりすると、筋肉の動きが制限され、「コリ」や「ゴリゴリ」としたしこりのような感覚を引き起こすことがあります。肩こりの原因も、筋肉そのものだけでなく、この筋膜のトラブルが関係していることが多いのです。
筋膜に異常が起きるとどうなる?
筋膜に異常が起きると、筋肉のスムーズな動きが妨げられ、肩こりの大きな原因となります。健康な筋膜は柔軟で滑らかに動きますが、姿勢の崩れや同じ動作の繰り返し、運動不足、ストレスなどが原因で筋膜が癒着したり、ねじれたりすると、筋肉が引っ張られたり動きにくくなったりします。
実際に肩を触って「ゴリゴリ」と感じる部分は、この筋膜に異常が生じている箇所であることが多く、白い線として確認できる筋膜が太くなっている部分を触っていることがわかります。これは筋膜が凝り固まり、厚みや硬さが出てしまっている状態です。
そのため、肩こりを根本から改善するためには、筋肉をただ揉みほぐすだけでは不十分で、筋膜を元の正常な状態に戻すことが大切です。特に効果的とされているのが「揉む」よりも「伸ばす」ケア。ストレッチや筋膜リリースといった方法で、筋膜の滑らかな動きを取り戻すことが、肩こり解消には欠かせません。
肩こりを改善するための方法:痛みを自分でケアする

肩こりの痛みを改善するためには、いくつかの効果的な方法があります。
1. 姿勢の改善で肩こりを防ぐ
多くの肩こりは、悪い姿勢が原因で起こります。特に長時間のデスクワークでは、以下の点に注意しましょう:
- モニターの高さ:ブロックなどで高さをだす、または椅子の高さを変えて、モニター画面の高さを目線と同じか少し下にする。
- 椅子の座り方:目線を下げないようにして、肩を下に下げると首が伸び背筋にしゃんとした軸ができます。20分に一回はこの姿勢を意識してください。背中の筋肉が働き支えることで、肩こりを起こす胸の筋肉や首の筋肉は緩んでくれます。
- キーボードとマウス:キーボードは体から遠くなると、頭が前に出て姿勢が悪くなってしまいますので、肘を曲げて届く場所に置きましょう。肘が開くと巻き肩になっていきます。脇は軽くしめて、肘が身体から離れないようにしましょう。
- 定期的に立ち上がって伸びをしましょう(1時間に1回程度)
- スマホを見るときは首を極端に下げない。ときどき遠くを見ることで目を休ませると、首肩コリが緩和されます。
2. 肩こり解消のストレッチ
肩こりの痛みを解消するのに効果的なストレッチをご紹介します:
肩甲骨をほぐすストレッチ
- 両肘を曲げて肩より上に上げる
- 息を吐きながら肩甲骨を寄せるイメージで両肘を後ろに引く
- 肩甲骨を寄せたまま肘を下げて力を抜く
- これを5回繰り返す
体側を伸ばすストレッチ
- 立った状態で片方の手を高く上げる
- 上げた手と反対側に体を倒す
- 20秒キープして元に戻る
- 左右交互に行う
肩甲骨はがし
- 仰向けに寝て両手を頭の上に伸ばす
- 肩甲骨を床から浮かせるイメージで、腕を上下に動かす
- 30秒ほど続ける
3. 温熱療法で血行を促進
肩こりの改善には温めることも効果的です:
- 温かい湯船にゆっくり浸かる
- 蒸しタオルを肩に置く
- カイロや温熱パッドを使用する
温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、痛みが軽減します。
4. 適度な運動で筋肉バランスを整える
運動不足も肩こりの原因の一つです。週に2〜3回、30分程度の有酸素運動を取り入れましょう。
- ウォーキング
特徴:全身を使ったリズミカルな有酸素運動で、心肺機能を高めながら血流促進が期待できます。
肩こり改善ポイント:
肩甲骨周りの血流がアップ:腕をしっかり振ることで、肩周辺の筋肉を自然に動かし、肩甲骨が動きやすくなります。
姿勢改善にも◎:正しいフォーム(背筋を伸ばし、視線は前へ)で歩くことで、猫背や巻き肩の改善にもつながります。
リラックス効果あり:軽い運動でストレスホルモンが減少し、精神的な緊張がほぐれ、筋肉のこわばりも改善。
おすすめ頻度:週2~3回、1回30分程度
(慣れてきたら毎日20分でもOK)
- 水泳
特徴:水中での運動は関節に優しく、筋肉に均等な負荷をかけられます。
肩こり改善ポイント:
肩回りの柔軟性がアップ:クロールや背泳ぎなどで肩関節を大きく動かすことで、固まった筋肉がほぐれます。
姿勢改善に効果的:水泳は体幹を自然に使うため、背筋が伸びやすくなり、姿勢が良くなることで肩の負担が軽減。
呼吸と連動するリズム運動:ゆっくりとした呼吸と全身運動が合わさることで、自律神経が整い、ストレス緩和にもつながります。
おすすめ頻度:週1~2回、30~45分(疲れすぎない範囲で)
- ヨガ
特徴:深い呼吸とゆったりしたポーズで筋肉をほぐし、心身のバランスを整える運動。
肩こり改善ポイント:
肩甲骨と首周りをじっくりストレッチ:猫のポーズ、鷲のポーズ、牛の顔のポーズなど、肩や背中の緊張を和らげるポーズが豊富。吐く息を意識することでポーズの間、筋肉を弛緩させます。肩が痛む場合、無理せず軽減ポーズに修正することが大切です。
呼吸によるリラックス効果:深い腹式呼吸で副交感神経が優位になり、筋肉の緊張が自然とほぐれます。
姿勢と重心の意識:体の使い方を見直すことで、無意識のうちに肩にかけていた負担が減ります。
おすすめ頻度:週2〜3回、1回20〜30分程度からスタート
- ピラティス
特徴:体幹を意識してコントロールされた動きを行い、筋肉のバランスを整えるエクササイズ。
肩こり改善ポイント:
肩のインナーマッスルを強化:小さな動きで肩周辺の深層筋にアプローチでき、筋肉の歪みを修正。いつも動かさない筋肉をしっかり動かすことで、筋肉のバランスや骨の位置のズレが改善し、偏った動きが減ることで、首肩の緊張が緩和し、動きが良くなっていきます。
体幹強化で姿勢改善:背骨を支える筋肉を鍛えることで、自然と肩の位置が整い、無駄な緊張が減少。
呼吸法で自律神経に働きかけ:ピラティス独自の呼吸(胸式ラテラル呼吸)は、肩回りの筋肉を意識的に動かすのに役立ちます。
おすすめ頻度:週1~2回、初心者はオンライン動画などから始めてもOK
特にヨガやピラティスは、姿勢改善や筋肉のバランス調整に効果的です。しかし、ポーズを追い求めて無理な動きを続けると、逆に姿勢を悪くしたり、症状が悪化してしまうため、適切に動いているか見てもらうことも大切です。
5. リラクゼーションでストレスを軽減
ストレスも肩こりの大きな原因です。リラックスする時間を作りましょう:
- 深呼吸
- メディテーション
- 趣味の時間を持つ
- 十分な睡眠をとる
6. 専門家のケアを受ける
自己ケアで改善しない場合は、専門家のサポートを受けましょう:
- 整体や鍼灸
- マッサージ
- 理学療法
- 医師の診察(症状が重い場合)
肩のしこりは自分でつぶしても大丈夫?つぶすよりも優しくケア

肩のしこりを自分で無理に押しつぶすことは、あまり推奨されません。その理由としては:
つぶさない方が良い理由
- 押すポイントがズレる可能性:肩のしこりは、筋肉の中でも特定の箇所にピンポイントに生じる「硬結」と呼ばれる状態です。正確な位置を捉えるには専門的な知識と触診の経験が必要で、自分で押す場合、わずかにポイントがズレるだけでも効果が薄れてしまいます。むしろ周囲の健康な筋肉に無駄な圧をかけてしまい、余計な疲労や違和感を招くこともあるため、セルフケアでは注意が必要です。
- 力加減が難しい:肩のしこりを自分で押す際、適切な力加減をコントロールするのは非常に難しいです。強すぎる圧力をかけると、筋肉を傷つけたり、炎症を起こす恐れがあります。逆に弱すぎても十分な効果が得られません。プロはしこりの深さや硬さに応じて圧力を調整できますが、自分では判断しにくく、かえって肩こりが悪化するリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
- 力づくで押すリスク:しこりを力づくで押しつぶそうとすると、無理な圧力がかかりやすく、筋肉や周囲の組織にダメージを与える可能性があります。特に指や腕の力だけで強引に押すと、適切な圧がかからず深部のコリには届かないまま表面だけを痛めてしまい、痛みや腫れを引き起こすこともあります。しこりは力で潰せば良いというものではなく、丁寧なアプローチが必要です。
- 道具を使うリスク:ツボ押し棒やボールなどの道具を使ってしこりをケアしようとする人もいますが、誤った使い方をすると逆効果になることがあります。角度や圧力が合っていないまま押すと、不快な痛みを伴い、筋膜や神経を刺激しすぎることもあります。特に自己流のやり方はリスクが高く、道具は正しい知識と指導のもとで使うべきです。
- 筋肉の繊維を傷つける可能性:しこりのある部分を適切な技術なしに無理に押すことで、筋肉の繊維そのものを傷つけてしまう恐れがあります。筋肉は繊細な構造をしており、強い圧力を受けると細かい損傷が生じ、逆に回復を遅らせたり痛みを強めたりすることがあります。本来なら優しく伸ばしたり温めたりして血流を促すケアが必要で、強く押すのは避けた方が無難です。
もし自分でケアする場合は、優しく押す程度にして、無理に強い力でつぶそうとしないことが大切です。人の手による適切なケアが最も効果的です。
まとめ:自分で肩こりを確認・改善するポイント

肩こりは、現代人にとって避けて通れない症状の一つですが、適切に対処することで改善が可能です。
- 肩こりは自分で触って確認できることもありますが、痛みなどの自覚症状も重要
- 9つのポイントでセルフチェックし、早めに対策を取ることが大切
- 肩こりの正体は筋肉だけでなく筋膜にも関係している
- 日常生活での姿勢改善、ストレッチ、適度な運動が基本的な対策
- 自分で無理に肩のしこりをつぶそうとせず、専門家のケアも検討を
肩こりは、放置すると頭痛や首の痛みなど他の症状にも発展する可能性があります。セルフチェックで自分の体の状態をよく知り、日々のケアを心がけることで、肩こりの痛みから解放され、快適な毎日を過ごしましょう。
