この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。
脊柱管狭窄症の注射治療でお悩みの方にとって、ブロック注射やステロイド注射は痛みやしびれを軽減する効果が期待できる選択肢です。ブロック注射(神経ブロック、硬膜外ブロック)やステロイド注射など、症状や状態によって適した注射の種類は異なります。この記事では、脊柱管狭窄症に対する様々な注射治療の効果や副作用、費用について詳しく解説します。手術を検討する前に、まずは保存療法としての注射治療の可能性を理解しましょう。
目次
脊柱管狭窄症と注射治療の基本
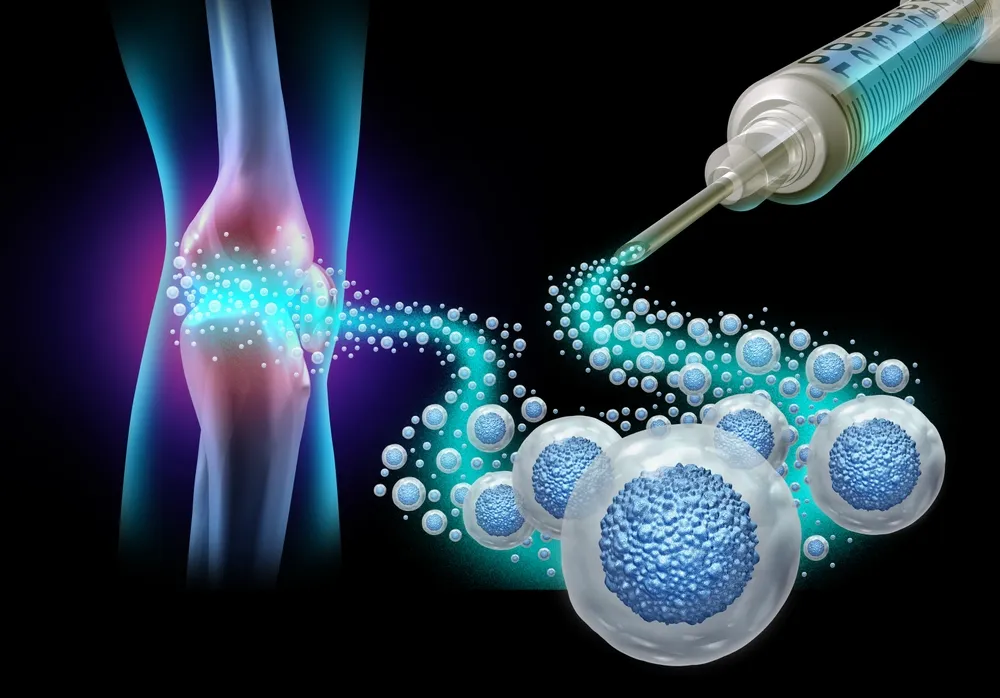
脊柱管狭窄症とは、背骨の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることで痛みやしびれなどの症状が現れる疾患です。加齢や変形などによって引き起こされることが多く、特に腰部脊柱管狭窄症は高齢者に多く見られます。
この状態では、神経の圧迫や炎症によって以下のような症状が現れます:
- 腰痛や下肢の痛み
- 足のしびれや感覚異常
- 間欠性跛行(一定距離を歩くと痛みで歩けなくなる症状)
- 長時間立っていられない
- 症状が進行すると排尿障害なども生じることがある
注射治療は、これらの症状を軽減するための保存療法の一つとして、多くの医療機関で行われています。薬物療法だけでは改善しない場合や、手術を避けたい場合に検討される治療法です。
間欠性跛行とは?
間欠性跛行とは、脊柱管狭窄症の特徴的な症状の一つで、一定の距離を歩くと足に痛みやしびれが生じて歩けなくなり、しばらく休むと再び歩けるようになる症状です。この症状は、歩行時に腰椎が反り返ることで脊柱管がさらに狭くなり、神経が圧迫されることで起こると考えられています。
脊柱管狭窄症の患者さんの多くは、まず保存療法から始めることが一般的です。注射治療は痛みやしびれを直接的に軽減できる点で、QOL向上に貢献します。
脊柱管狭窄症に対する注射の種類と特徴

脊柱管狭窄症に対して行われる注射治療には、主に以下のような種類があります。それぞれ特徴や適応が異なるため、症状や状態に合わせて適切な治療法が選択されます。
神経ブロック注射とは?
神経ブロックは、痛みを伝えている神経に局所麻酔薬を注射し、神経の働きを一時的に遮断する治療法です。これにより、痛みが軽減される可能性があります。
神経ブロックの主な種類には以下のようなものがあります:
- 神経根ブロック:圧迫されている特定の神経根に注射を行います
- 腰神経叢ブロック:腰部の神経叢を標的とした注射治療
- 仙骨裂孔ブロック:仙骨裂孔という穴から行うブロック注射
硬膜外ブロック注射とは?
硬膜外ブロックは、脊髄を包む硬膜と脊柱の間の空間(硬膜外腔)に局所麻酔薬やステロイドを注射します。神経の炎症を抑え、痛みを軽減する効果が期待できます。
腰部脊柱管狭窄症による下肢のしびれや痛みに対して特に効果的とされており、ペインクリニックや整形外科で広く行われている治療法です。
ステロイド注射とは?
ステロイド注射は、炎症を抑える効果があるステロイド剤を注射することで、神経の炎症による痛みを軽減します。単独で使用されることもありますが、多くの場合、上記のブロック注射と組み合わせて使用されます。
ステロイド剤には強い抗炎症作用があり、神経周囲の炎症を効果的に抑えることができますが、長期的・頻繁な使用には注意が必要です。
トリガーポイント注射
トリガーポイント注射は、筋肉の緊張や痛みのある特定のポイント(トリガーポイント)に局所麻酔薬を注射する治療法です。脊柱管狭窄症に伴う筋緊張の緩和に効果が期待できます。
| 注射の種類 | 主な特徴 | 効果 | 適応例 |
|---|---|---|---|
| 神経ブロック | 痛みを伝える神経の働きを一時的に遮断 | 痛みやしびれの即時的な軽減 | 特定の神経根が圧迫されている場合 |
| 硬膜外ブロック | 硬膜外腔に薬剤を注入 | 広範囲の痛み軽減、炎症抑制 | 下肢のしびれや痛みを伴う腰部脊柱管狭窄症 |
| ステロイド注射 | 強力な抗炎症作用 | 炎症の抑制、痛みの軽減 | 神経の炎症が強い場合、他の注射と併用 |
| トリガーポイント注射 | 筋肉の緊張箇所に直接注射 | 筋緊張の緩和、血行改善 | 筋肉の緊張を伴う腰痛 |
注射治療の期待できる効果と限界

脊柱管狭窄症に対する注射治療では、以下のような効果が期待できます。ただし、その効果には個人差があり、また一時的なものであることを理解しておくことが重要です。
注射治療で期待できる効果
ブロック注射は、単に痛みを軽減するだけでなく、血行を改善したり、筋肉の緊張を和らげたりする効果も期待できます。これにより、日常生活の質を向上させることができます。
具体的には、以下のような効果が期待できます:
- 痛みやしびれの軽減
- 歩行距離の延長(間欠性跛行の改善)
- 日常生活動作の改善
- 薬物療法の補助(薬の使用量を減らせる可能性)
- 神経周囲の炎症抑制
- 筋肉の緊張緩和
- 血行の改善
効果の持続期間
注射治療の効果の持続期間には個人差があり、数時間から数週間、長い場合は数カ月続くこともあります。一般的には、以下のような傾向があります:
- 局所麻酔薬のみの場合:数時間~数日
- ステロイド剤併用の場合:数日~数週間、場合によっては数カ月
効果が持続する間に、リハビリテーションや運動療法を組み合わせることで、より良い治療成果が期待できます。
注射治療の限界
注射治療は保存療法の一つであり、根本的な脊柱管の狭窄を解消するものではありません。以下のような限界があることを理解しておく必要があります:
- 効果は一時的であることが多い
- 繰り返し治療が必要になる場合がある
- 症状の重症度によっては効果が限定的
- 狭窄の原因そのものは改善しない
- 進行性の症例では、最終的に手術が必要になることもある
注射治療は対症療法であり、脊柱管狭窄症の原因そのものを取り除くものではありません。しかし、手術に比べて低侵襲であり、適切に行われれば患者さんのQOL向上に大きく貢献します。
知っておくべき注射治療の副作用とリスク

脊柱管狭窄症に対する注射治療は比較的安全な治療法ですが、いくつかの副作用やリスクがあることを理解しておくことが重要です。
一般的な副作用
注射治療に伴う一般的な副作用には、以下のようなものがあります:
- 注射部位の痛みや腫れ
- 一時的な血圧上昇
- 一時的な血糖値上昇(ステロイド使用時)
- 頭痛(特に硬膜外注射後)
- 顔面紅潮
- めまいや吐き気
これらの副作用のほとんどは一時的なもので、数日以内に自然に改善することが多いです。
稀に起こりうる重大なリスク
稀ではありますが、以下のような重大なリスクもあることを知っておくべきです:
- 感染症
- 出血(特に血液凝固異常がある場合)
- 神経損傷
- 硬膜穿刺による髄液漏(硬膜外注射の場合)
- アレルギー反応
医療安全に関する情報によると、これらのリスクを最小限に抑えるためには、経験豊富な医師による適切な施術が重要です。
ステロイド注射の特有のリスク
ステロイド注射には、以下のような特有のリスクがあります:
- 免疫機能の一時的な低下
- 皮膚や皮下組織の萎縮(注射部位)
- 色素沈着
- ステロイドの全身的な副作用(長期・頻回使用時)
これらのリスクは、ステロイドの使用量や頻度を適切に管理することで軽減できます。
注射治療の流れと費用について

脊柱管狭窄症の注射治療を受ける際の一般的な流れと、気になる費用について解説します。
治療の流れ
一般的な注射治療の流れは以下の通りです:
- 初診・診察:症状の確認、身体診察
- 検査:レントゲン、MRI、CT等による画像診断
- 診断・治療計画:脊柱管狭窄症の診断と治療方針の決定
- インフォームドコンセント:治療の説明と同意
- 注射治療:
- 体位の調整(多くの場合、うつ伏せ)
- 注射部位の消毒
- 場合によっては、X線透視下で正確に注射
- 注射の実施(10~20分程度)
- 治療後の観察:副作用や合併症がないか確認(30分~1時間)
- 経過観察・フォローアップ:効果の確認と必要に応じた追加治療
注射治療自体は外来で行われることが多く、通常は日帰りで受けることができます。
治療の費用
注射治療の費用は、治療の種類や医療機関によって異なります。以下は一般的な目安です:
| 治療内容 | 自己負担額(3割負担の場合) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 神経ブロック注射 | 約3,000〜7,000円 | 施術回数や使用薬剤により変動 |
| 硬膜外ブロック注射 | 約5,000〜10,000円 | X線透視使用により高額になる場合も |
| 初診料・再診料 | 約1,000〜3,000円 | 医療機関の規模により異なる |
| MRI検査(必要時) | 約5,000〜10,000円 | 施設や撮影部位により異なる |
保険適用外の治療や自由診療の場合は、上記よりも高額になることがあります。詳細な費用については、受診する医療機関に直接お問い合わせください。
注射治療が適しているケース・適さないケース

脊柱管狭窄症の注射治療が特に効果的なケースと、あまり適さないケースについて解説します。
注射治療が適しているケース
以下のようなケースでは、注射治療が特に効果的である可能性が高いです:
- 保存的治療(薬物療法、理学療法など)で十分な効果が得られない場合
- 手術を避けたい、または手術が適さない状態の患者
- 神経の圧迫が中等度までで、明らかな神経障害がない場合
- 痛みやしびれが主な症状である場合
- 間欠性跛行(歩行時の痛み)が主訴の場合
- 炎症が症状の原因と考えられる場合
- 高齢や合併症のため手術リスクが高い患者
注射治療があまり適さないケース
一方、以下のようなケースでは、注射治療の効果が限定的であったり、他の治療法を優先すべき場合があります:
- 重度の神経麻痺や筋力低下がある場合
- 膀胱直腸障害(排尿・排便障害)がある場合
- 進行性の神経症状がある場合
- 注射部位に感染がある場合
- 出血傾向や凝固異常がある場合
- 注射に使用する薬剤にアレルギーがある場合
- 過去の注射治療で効果がなかった場合
これらのケースでは、手術的治療や他の保存療法を検討する必要があるかもしれません。脊柱管狭窄症の手術療法については、専門医とよく相談することをおすすめします。
専門家の見解
脊柱管狭窄症の注射治療については、個々の患者の状態に応じた適切な治療法の選択が重要です。症状の性質、程度、発症期間、患者の全身状態、生活背景などを総合的に評価し、最適な治療法を決定することが求められます。
注射治療は、手術療法と薬物療法の中間に位置する治療法として、適切に使用されれば多くの患者のQOL向上に貢献します。ただし、その限界を理解し、必要に応じて他の治療法との併用や切り替えを検討することも重要です。
信頼できる病院・クリニックの選び方

脊柱管狭窄症の注射治療を受ける際には、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にしてください。
専門性の高さをチェック
脊柱管狭窄症の治療に関しては、以下のような診療科や専門医がいる医療機関を選ぶと良いでしょう:
- 整形外科
- 脊椎専門クリニック
- ペインクリニック(痛みの専門医)
- 脊椎・脊髄外科専門医がいる施設
また、注射治療(特に神経ブロックや硬膜外ブロック)の実績が豊富な医師がいる医療機関を選ぶことも重要です。
設備や治療環境
注射治療、特にX線透視下での正確な注射を行うためには、適切な設備が整っていることが重要です。以下のような設備があるかチェックしましょう:
- X線透視装置
- MRIやCTなどの画像診断機器
- 清潔な処置室
- 緊急時の対応設備
総合的なアプローチ
注射治療だけでなく、総合的な治療アプローチができる医療機関が理想的です。以下のような点を考慮しましょう:
- 薬物療法、理学療法、装具療法など他の保存療法も提供している
- 必要に応じて手術も検討できる体制がある、または連携病院がある
- リハビリテーション部門が充実している
- 椎間板ヘルニアなど関連疾患にも対応できる
自分の症状や状態に合わせた最適な治療選択肢を提示してくれる医療機関を選ぶことが、治療成功の鍵となります。
脊柱管狭窄症の注射治療における最新の動向

脊柱管狭窄症の注射治療は、医学の進歩とともに新しい技術や方法が導入されています。ここでは、最近の動向について簡単に紹介します。
超音波ガイド下注射
従来のX線透視に加えて、超音波ガイド下で行う注射治療が増えています。超音波を用いることで、放射線被曝なしに神経や周囲組織をリアルタイムで確認しながら、より安全かつ正確に注射を行うことができます。
再生医療の応用
PRP(多血小板血漿)療法や幹細胞を用いた注射治療など、再生医療の技術を応用した治療法も研究・導入されつつあります。これらは従来の注射治療よりも長期的な効果が期待できる可能性がありますが、まだ研究段階のものも多く、保険適用外の治療であることが多いです。
薬剤の進化
注射に使用する薬剤についても研究が進み、より効果的で副作用の少ない薬剤や、効果の持続時間が長い徐放性の薬剤なども開発されています。これにより、治療の効果や患者さんの負担軽減が期待されています。
脊柱管狭窄症の注射治療に関するよくある質問

Q. 脊柱管狭窄症の注射治療は痛いですか?
A. 注射時に若干の痛みを感じることはありますが、多くの場合、注射部位を局所麻酔で事前に麻痺させるため、強い痛みを感じることは少ないです。ただし、注射後に一時的に注射部位の痛みや不快感を感じることがあります。医師や看護師に不安を伝えれば、できるだけ痛みを軽減する工夫をしてくれるでしょう。
Q. 注射治療の効果はどのくらい続きますか?
A. 効果の持続期間には個人差があり、数日から数ヶ月と幅があります。一般的には局所麻酔薬のみの場合は数時間〜数日、ステロイド併用の場合は数週間〜数ヶ月効果が持続することが多いです。効果が短い場合は、繰り返し治療を行うことで長期的な改善が得られることもあります。
Q. 注射治療は何回まで受けられますか?
A. 注射治療の回数に厳密な制限はありませんが、特にステロイド注射は過度に頻回に行うと副作用のリスクが高まるため、一般的には年に3〜4回程度までとされることが多いです。過度に頻回な注射は副作用リスクを高める可能性があります。具体的な回数は、症状の程度や効果の持続期間、全身状態などを考慮して、担当医師が判断します。
Q. 注射治療で脊柱管狭窄症は完治しますか?
A. 注射治療は対症療法であり、脊柱管の狭窄自体を解消するものではないため、完治を期待することは難しいです。しかし、痛みやしびれなどの症状を軽減し、日常生活の質を向上させることができます。症状のコントロールがうまくいけば、手術を回避したり、延期したりすることも可能です。
Q. 注射治療と他の治療法を併用できますか?
A. はい、注射治療は他の保存療法(薬物療法、理学療法、装具療法など)と併用することで、より効果的な治療が期待できます。特に、注射で痛みが軽減している間にリハビリテーションを行うことで、筋力強化や柔軟性の向上が図れ、長期的な改善につながることがあります。治療計画については、担当医師と相談しましょう。
Q. 注射治療後の注意点はありますか?
A. 注射治療後は、以下のような点に注意するとよいでしょう:①当日は激しい運動や入浴は避ける ②痛みが軽減してもすぐに無理な活動をしない ③注射部位の異常(発熱、腫れ、強い痛みなど)があれば医師に相談する ④効果の経過を記録しておく ⑤指示された通院・フォローアップを守る。詳細な注意点については、治療を行う医療機関からの指示に従ってください。
Q. 手術と注射治療はどう選べばよいですか?
A. 手術と注射治療の選択は、症状の重症度、日常生活への影響度、年齢、全身状態などを総合的に考慮して判断します。一般的に、①保存療法(薬物療法や理学療法)で効果不十分な場合にまず注射治療を検討 ②注射治療でも十分な効果が得られない場合や、進行性の神経症状、膀胱直腸障害がある場合には手術を検討、という流れになることが多いです。個々の状況に応じた最適な選択については、専門医とよく相談することが重要です。
まとめ:脊柱管狭窄症の注射治療を検討する際のポイント

脊柱管狭窄症の注射治療は、痛みやしびれなどの症状を軽減する効果的な選択肢の一つですが、すべての患者さんに適しているわけではありません。以下の点を念頭に置いて、自分に合った治療法を検討しましょう。
- 適切な診断が重要:まずは正確な診断を受け、症状の原因や程度を把握することが大切です。
- 治療の限界を理解する:注射治療は対症療法であり、根本的な解決法ではないことを理解しておきましょう。
- 総合的なアプローチ:注射治療単独ではなく、薬物療法、運動療法、生活習慣の改善など、複合的なアプローチが効果的です。
- 専門医に相談:治療に関する疑問や不安は、専門医に相談し、十分な説明を受けた上で決断することが重要です。
脊柱管狭窄症の治療は、一人ひとりの症状や生活スタイル、年齢などによって最適な方法が異なります。この記事が、あなたの治療選択の参考になれば幸いです。

