この記事は「セルフケア整体 院長・森下 のぶひで(NOBU先生)」の監修のもと作成されています。
首と頭痛の両方が痛い場合、症状によって受診する科が異なります。首の痛みだけなら整形外科が、頭痛も伴う場合は脳神経外科や頭痛外来を受診するのが適切です。この記事では、あなたの症状に合った診療科の選び方、考えられる原因、そして緊急受診が必要なケースまで詳しく解説します。つらい症状でどこに行けばいいか迷ったら、ぜひ参考にしてください。
目次
まず結論:首の痛みと頭痛、何科を受診すべき?

首の痛みと頭痛でお悩みの場合、症状の特徴によって受診すべき診療科が変わります。以下の表で、あなたの症状に最適な診療科をチェックしてみましょう。
| 症状 | 最適な診療科 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 首の痛みのみ(肩こりを伴う) | 整形外科 | 姿勢指導、リハビリ、薬物療法 |
| 首の痛みと頭痛が同時に起こる | 脳神経外科・脳神経内科 | CT/MRI検査、薬物療法 |
| 頭痛が主で首の痛みを伴う | 頭痛外来(脳神経内科) | 頭痛専門の診断・治療 |
| 首の腫れや喉の痛みを伴う | 耳鼻咽喉科 | 炎症治療、抗生物質など |
| 突然の激しい頭痛と首の痛み | 救急外来 | 緊急検査、適切な専門科へ |
首の痛みから生じる頭痛は、整形外科的な問題が原因となっていることが多いですが、頭痛と首の痛みが同時に発症する場合は、神経学的な問題の可能性も考慮すべきです。
症状セルフチェック:あなたの首痛・頭痛はどのタイプ?

最適な診療科を選ぶためには、まず自分の症状がどのタイプに当てはまるか確認しましょう。以下のチェックリストで、あなたの症状に最も近いものを見つけてください。
首の痛みが主体の場合(整形外科向き)
- 首を動かすと痛みが強くなる
- 長時間のデスクワークや同じ姿勢の後に痛みが出る
- 肩こりや背中の痛みを伴うことが多い
- 腕や手にしびれや痛みが放散する
- 頭痛がある場合も、首の動きに関連して変化する
首の痛みが主体で、姿勢や動作に関連して症状が変化する場合は、整形外科を受診しましょう。
頭痛が主体で首の痛みも伴う場合の受診先

頭痛が主体で首の痛みも伴う場合(脳神経外科・内科向き)
- 頭がズキズキと脈打つような痛み
- 頭が締め付けられるような痛み
- 光や音に過敏になる
- 吐き気やめまいを伴うことがある
- 首の痛みは頭痛に続いて出現することが多い
頭痛が主体で、光・音への過敏さや吐き気などの随伴症状がある場合は、脳神経外科や脳神経内科を受診しましょう。
緊急性の高い症状と対応

突然の激しい頭痛と首の痛み(緊急受診が必要)
- 今まで経験したことのないような激しい頭痛
- 「頭の中で何かが破裂した」ような感覚
- 首の後ろ(後頭部)に強い痛みがある
- 意識障害や言語障害を伴う
- 発熱や嘔吐を伴う
これらの症状がある場合は、くも膜下出血などの重篤な疾患の可能性があります。迷わず救急車を呼び、緊急受診してください。
整形外科での診療内容
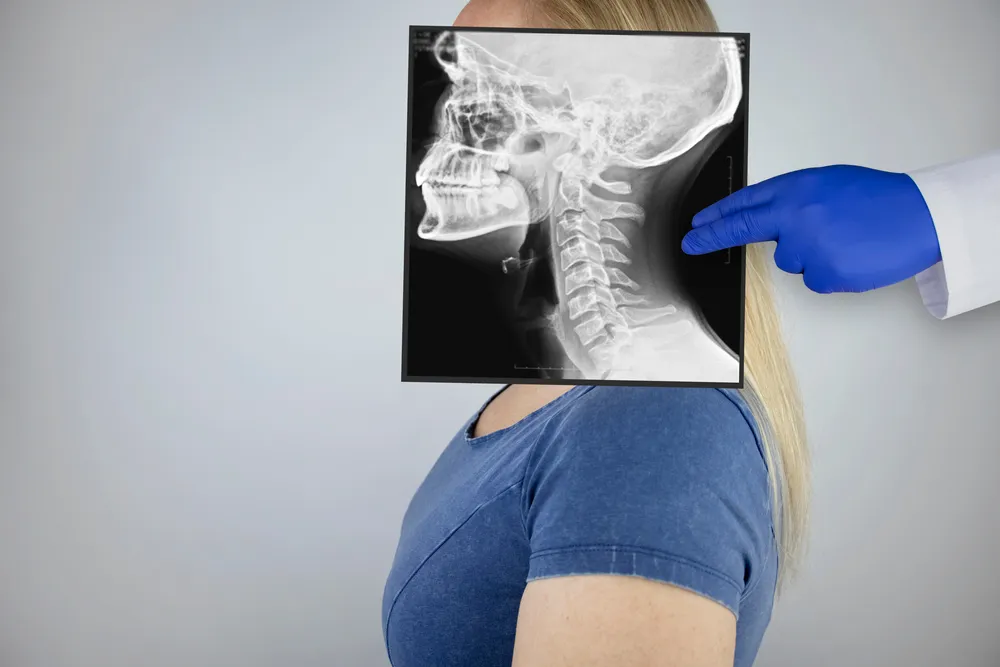
整形外科では、首の痛みの原因となる筋肉や骨、関節の問題を診断・治療します。
整形外科で行われる検査
- レントゲン検査(頚椎の変形や骨の状態を確認)
- MRI検査(頚椎椎間板ヘルニアなどの確認)
- 神経学的検査(しびれや筋力低下の有無を確認)
整形外科での主な治療法
- 薬物療法(鎮痛剤、筋弛緩剤など)
- 理学療法・リハビリテーション
- 姿勢指導や生活習慣の改善
- 頚椎カラー(首の安静を保つ)
- トリガーポイント注射(筋肉の緊張緩和)
脳神経外科・脳神経内科の役割

脳神経外科や脳神経内科では、頭痛の原因となる脳や神経系の問題を診断・治療します。
脳神経外科・内科での検査方法
- CT検査(脳出血やくも膜下出血の確認)
- MRI検査(脳腫瘍や血管異常の確認)
- 血液検査(炎症マーカーなどの確認)
- 神経学的検査(脳神経機能の評価)
脳神経外科・内科での治療アプローチ
- 薬物療法(片頭痛薬、緊張型頭痛治療薬など)
- 神経ブロック注射
- 生活習慣指導(睡眠、食事、ストレス管理)
- 手術療法(必要な場合のみ)
耳鼻咽喉科の診療内容

首の痛みの中でも、特に前頸部(のど)の痛みや腫れがある場合は耳鼻咽喉科が適しています。
耳鼻咽喉科での検査方法
- 喉頭ファイバースコープ検査
- 超音波検査(甲状腺や首のリンパ節の確認)
- 血液検査(炎症反応の確認)
耳鼻咽喉科での治療法
- 抗生物質(細菌感染の場合)
- 抗炎症薬
- うがい薬や喉スプレー
首の痛みと頭痛の関連性とメカニズム

首の痛みと頭痛は、密接に関連している可能性があります。その理由を解説します。
緊張型頭痛と首の関係
緊張型頭痛は、首や肩の筋肉の緊張が原因となって発生することが多い頭痛です。長時間のデスクワークや不良姿勢、ストレスなどで首の筋肉が緊張すると、その緊張が頭部にまで広がり、頭痛を引き起こす傾向があります。
緊張型頭痛の患者さんの多くは、首や肩の筋肉に過度の緊張があります。この筋緊張を改善するだけで、頭痛が軽減するケースも少なくありません。
頚椎由来の頭痛
頚椎(首の骨)の異常が原因で頭痛が起こる可能性もあります。頚椎症や頚椎椎間板ヘルニアなどの疾患では、神経が圧迫されることにより、首の痛みだけでなく頭痛も引き起こされる傾向がみられます。この場合、整形外科での治療が必要になる可能性があります。
片頭痛と首の痛み
片頭痛の患者さんは、頭痛発作の前兆や発作中に首の痛みを感じることがある可能性があります。また、片頭痛発作後に首の筋肉が緊張して痛みを生じることもあるとされています。
危険な頭痛・首の痛みのサイン

首の痛みや頭痛の中には、緊急性の高い危険な症状があります。以下のサインがある場合は、迷わず救急受診してください。
| 危険なサイン | 考えられる疾患 | 対応 |
|---|---|---|
| 突然の激しい頭痛(今までで最悪の頭痛) | くも膜下出血 | 救急車を呼ぶ |
| 頭痛・首の痛みに加え、発熱や意識障害 | 髄膜炎 | 救急車を呼ぶ |
| 首の痛みと共に手足のしびれや脱力 | 頚髄損傷・圧迫 | すぐに脳神経外科 |
| 頭痛と視力障害・複視(ものが二重に見える) | 脳腫瘍・動脈解離 | すぐに脳神経外科 |
| 首の痛みと嚥下困難・呼吸困難 | 喉頭蓋炎・扁桃周囲膿瘍 | 救急で耳鼻咽喉科 |
上記のような危険なサインがある場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診してください。命に関わる可能性があります。
自分でできる応急処置

病院を受診する前に、自分でできる対処法をご紹介します。ただし、これらは一時的な対処法であり、症状が続く場合は必ず医療機関を受診してください。
姿勢の改善方法
首の痛みや頭痛の多くは、不良姿勢が原因となっている可能性があります。特にスマートフォンやパソコンを使用する際の「ストレートネック」や「猫背」は、首への負担を増加させるとされています。
- デスクワーク時は、背筋を伸ばし、画面が目の高さになるよう調整する
- スマートフォンは目線を下げすぎないよう、なるべく高い位置で見る
- 1時間に一度は姿勢を変え、首を軽くストレッチする
ストレッチと筋肉ケア方法

効果的なストレッチ法
首の筋肉の緊張を和らげるストレッチは、痛みの予防と緩和に効果的とされています。
- 首を前後左右にゆっくり傾ける(痛みを感じない範囲で)
- 肩を上下に動かし、肩甲骨周りの筋肉をほぐす
- 入浴時に温めながら、首や肩をマッサージする
温熱・冷却療法の適用
症状に応じて、温めたり冷やしたりすることで痛みを和らげることができる可能性があります。
- 筋肉の緊張からくる痛み → 温める(蒸しタオル、カイロなど)
- 炎症や急性の痛み → 冷やす(アイスパックなど)
適切な休息と睡眠
疲労は首の痛みや頭痛の大きな原因となる可能性があります。十分な休息と質の良い睡眠を心がけましょう。
- 首をサポートする適切な枕を使用する
- 横向きに寝る場合は、首がねじれないよう注意する
- 定期的に休憩を取り、目や首を休める
専門家による見解
首の痛みと頭痛は密接に関連している可能性があり、一方が原因で他方が発生する傾向がみられます。特に緊張型頭痛では、首や肩の筋肉の緊張が頭痛の直接的な原因となる可能性がありますが、これは姿勢の改善やストレス管理によって改善できるケースもあるとされています。
一方で、脳の病気が原因で頭痛が生じ、それに伴って首の痛みが出ることもある可能性があります。症状が2週間以上続く場合や、痛みが強い場合は、専門医に相談することが重要です。特に突然の激しい頭痛は、命に関わる緊急事態の可能性があるため、迷わず救急受診してください。
病院選びのポイント

適切な診療科を選んだら、次は病院選びです。以下のポイントを参考にしてください。
総合病院とクリニックの違い
- 総合病院のメリット: 各科の連携がスムーズ、精密検査(MRI/CTなど)がすぐに可能
- クリニックのメリット: 待ち時間が短い、専門特化した治療が受けられることも
専門医の確認方法
首の痛みや頭痛に詳しい専門医がいる医療機関を選ぶと安心です。
- 脳神経外科専門医
- 日本頭痛学会認定頭痛専門医
- 日本整形外科学会専門医(脊椎脊髄病医)
受診前の準備と情報整理

かかりつけ医からの紹介
症状が複雑で判断が難しい場合は、まずかかりつけ医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法とされています。
受診前に整理すべき情報
医療機関を受診する際は、以下の情報を整理しておくと診察がスムーズに進む可能性があります。
- いつから症状があるか
- 痛みの性質(ズキズキ、ジンジン、締め付けられるなど)
- 痛みの強さ(10段階で表現)
- 痛みが強くなる状況や時間帯
- 随伴症状(吐き気、めまい、視覚症状など)
- 服用中の薬
- 過去の病歴
これらの情報を医師に伝えることで、より正確な診断と適切な治療につながる可能性があります。
首痛と頭痛に関するよくある質問

Q. 首の痛みと頭痛が同時に起こるのはなぜですか?
A. 首の痛みと頭痛が同時に起こる主な理由は、首と頭部が神経学的に密接に連携しているためです。首の筋肉の緊張や頚椎の問題が脳に送られる信号に影響を与え、頭痛を引き起こすことがある可能性があります。特に緊張型頭痛では、首や肩の筋肉の緊張が直接的な原因となることが多いとされています。また、片頭痛の前兆や発作中に首の痛みを感じることもあるとされています。逆に、脳の疾患が原因で頭痛が発生し、それに伴って首の痛みが生じる可能性もあります。
Q. 首の痛みと頭痛が続く場合、いつ病院を受診すべきですか?
A. 首の痛みと頭痛が2週間以上続く場合や、通常の鎮痛剤で改善しない場合は医療機関への受診を検討しましょう。また、以下のような症状がある場合は早急に受診することをお勧めします:
・突然の激しい頭痛(これまで経験したことのないような痛み)
・発熱や嘔吐を伴う頭痛
・頭痛とともに意識障害や言語障害がある
・首の痛みと共に手足のしびれや脱力がある
・頭痛と視力障害や複視(ものが二重に見える)がある
特に上記の症状がある場合は、緊急性が高い可能性があるため、救急外来を受診することをお勧めします。
Q. 首の痛みから起こる頭痛と、脳の病気による頭痛はどう見分けますか?
A. 首の痛みから起こる頭痛(頚原性頭痛)と脳の病気による頭痛を完全に見分けるには専門医の診断が必要ですが、一般的な違いとして以下のポイントがあります:
【首の痛みから起こる頭痛の特徴】
・首を動かすと痛みが変化する
・後頭部や頭の後ろ側に痛みが集中する
・じわじわとした鈍い痛みが多い
・首や肩の筋肉に硬さや圧痛がある
・姿勢を改善すると痛みが軽減することがある
【脳の病気による頭痛の特徴】
・突然の激しい頭痛(くも膜下出血など)
・徐々に強くなる持続的な頭痛(脳腫瘍など)
・嘔吐や意識障害などの神経症状を伴う
・光や音に過敏になる(片頭痛)
・頭の片側だけが拍動性に痛む(片頭痛)
これらの症状はあくまで目安であり、正確な診断には医師による診察と適切な検査が必要です。自己判断は危険な場合があるため、心配な症状があれば医療機関を受診してください。
Q. 首の痛みと頭痛の予防のために日常生活で気をつけることは?
A. 首の痛みと頭痛の予防には以下の日常習慣が効果的である可能性があります:
【姿勢の改善】
・デスクワーク時は背筋を伸ばし、画面を目線の高さに調整する
・スマホの使用時間を減らし、見る時は目線を極端に下げない
・定期的に姿勢をチェックし、猫背やストレートネックを避ける
【ストレス管理】
・定期的なリラクゼーション(深呼吸、瞑想など)
・十分な睡眠と休息
・趣味や運動でストレス発散
【生活習慣】
・適度な運動(特に首や肩のストレッチ)
・規則正しい食事と水分摂取(特に水分不足は頭痛の原因になる可能性も)
・アルコールやカフェインの過剰摂取を避ける
【睡眠環境の整備】
・首をサポートする適切な枕の使用
・寝る姿勢に気をつける(特に横向きで首がねじれないよう)
・快適な睡眠環境(温度、湿度、照明)を整える
これらの習慣を日常的に意識することで、首の痛みや頭痛のリスクを軽減できる可能性があります。
Q. 首の痛みと頭痛に効果的なストレッチ方法はありますか?
A. 首の痛みと頭痛を和らげるための効果的なストレッチ方法としては、以下が挙げられます:
【首のストレッチ】
1. 首の回旋:ゆっくりと首を右回り、左回りに回す(5回ずつ)
2. 首の側屈:右耳を右肩に、左耳を左肩に近づける(各5秒×3セット)
3. 首の前屈・後屈:あごを胸に引き、次に天井を見上げる(各5秒×3セット)
【肩のストレッチ】
1. 肩の上下運動:肩をすくめて5秒キープし、力を抜く(5回繰り返す)
2. 肩甲骨寄せ:胸を張り、肩甲骨を背中の中央に寄せる(10秒×3セット)
【胸のストレッチ】
1. ドアフレームストレッチ:ドアの枠に両手をつけて、体を前に倒す(15秒×2セット)
【注意点】
• 痛みを感じる場合はすぐに中止する
• ゆっくりと呼吸しながら行う
• 急激な動きは避け、ゆっくりと行う
• 1日3回程度を目安に継続的に行う
これらのストレッチは首や肩の筋肉の緊張を和らげ、血流を改善することで、痛みの緩和に役立つ可能性があります。ただし、激しい痛みがある場合や、ストレッチ後に症状が悪化する場合は、医師に相談してください。
Q. 首の痛みと頭痛に市販薬は効果がありますか?
A. 首の痛みと頭痛に対する市販薬は、一時的な症状緩和には効果がある場合がありますが、根本的な原因治療にはならない可能性があります。市販薬を使用する際の注意点は以下の通りです:
【効果が期待できる市販薬】
• 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):イブプロフェン、ロキソプロフェンなど
• アセトアミノフェン:比較的副作用が少なく、頭痛に効果的とされている
• 配合剤:カフェインなどを含む複合的な頭痛薬
【使用上の注意点】
• 用法・用量を守る(過剰摂取は副作用のリスクを高める可能性がある)
• 連続して3日以上使用しない(薬物乱用頭痛のリスクがある可能性)
• 胃腸障害や持病がある方は医師に相談してから使用する
• 症状が改善しない場合は自己判断で継続せず、医療機関を受診する
【市販薬が適さない可能性がある場合】
• 突然の激しい頭痛
• 発熱や嘔吐を伴う頭痛
• 意識障害や視覚異常を伴う場合
• 妊娠中や授乳中の方
• 持病がある方や他の薬を服用中の方
市販薬はあくまで一時的な対処法です。症状が2週間以上続く場合や、市販薬で改善しない場合は、早めに医療機関を受診してください。
Q. 子供の首の痛みと頭痛はどう対処すべきですか?
A. 子供の首の痛みと頭痛への対処は、大人とは異なる配慮が必要です:
【医療機関への受診目安】
• 3歳未満の乳幼児で頭痛を訴える場合(早めに小児科受診)
• 痛みで夜間に目が覚める
• 発熱や嘔吐を伴う頭痛
• 頭を打った後の頭痛
• 頭痛の頻度や強さが増している
• 性格や行動の変化が見られる
【家庭での対処法】
• 十分な休息をとらせる
• 水分を十分に摂らせる
• 明るい光や大きな音から遠ざける
• 冷たいタオルを額に当てる(熱がない場合)
• 子供用の適切な用量の解熱鎮痛薬(医師の指示に従って)
【生活習慣の見直し】
• 十分な睡眠時間の確保
• 規則正しい食事
• スマートフォンやゲームの使用時間制限
• 適度な運動の奨励
• ストレスの原因(学校、友人関係など)の把握
【注意点】
• 子供自身が症状を正確に伝えられない場合があるため、行動の変化に注意する
• 市販薬は小児科医の指示なく使用しない
• 子供の頭痛日記をつけて、パターンや引き金を把握する
子供の頭痛は、大人と異なり、成長や発達に関連する場合もあります。心配な症状がある場合は、自己判断せず小児科や小児神経科を受診することをお勧めします。

