この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。
「首痛(くびいた・しゅつう)」という言葉を目にしたとき、正しい読み方に迷ったことはありませんか?この記事では、「首痛」の正しい読み方から、その意味、症状、原因まで詳しく解説します。医学的な観点からの「首痛(しゅつう)」の捉え方も紹介するので、首の不調でお悩みの方は参考にしてください。「首痛」と一言で言っても、その症状や原因は様々です。正しい知識を身につけて、つらい首の痛みを改善しましょう。
実はその頑固な不調、根本的な原因は意外な場所、手首にある可能性が高いんです。手首と首や肩って関係あるのって思いますよね。でも私たちの体は全部繋がっています。
目次
「首痛」の正しい読み方とは?

「首痛」の読み方には、主に2つの読み方があります。
| 読み方 | 特徴 | 主な使用場面 |
|---|---|---|
| しゅつう | 音読み(漢語由来) | 医学的・専門的な文脈で多く使用 |
| くびいた | 訓読み(和語由来) | 日常会話や一般的な文脈で使用 |
基本的には、どちらの読み方も間違いではありません。ただし、使用される文脈によって適切な読み方が異なる場合があります。特に医学的な文脈では「しゅつう」という読み方が主流です。
なぜ「首痛」の読み方は複数あるのか?

日本語の漢字には、音読みと訓読みという2つの読み方の体系があります。「首痛」の場合も同様に:
- 「首(くび)」:訓読みでは「くび」、音読みでは「しゅ」
- 「痛(いた・つう)」:訓読みでは「いた(い)」、音読みでは「つう」
このように、それぞれの漢字に音読みと訓読みがあるため、組み合わせによって複数の読み方が生まれます。歴史的には、日本古来の言葉(和語)に対応する訓読みと、中国から伝わった読み方である音読みが混在しているためです。
医学用語としての「首痛」の読み方と一般的な使い方
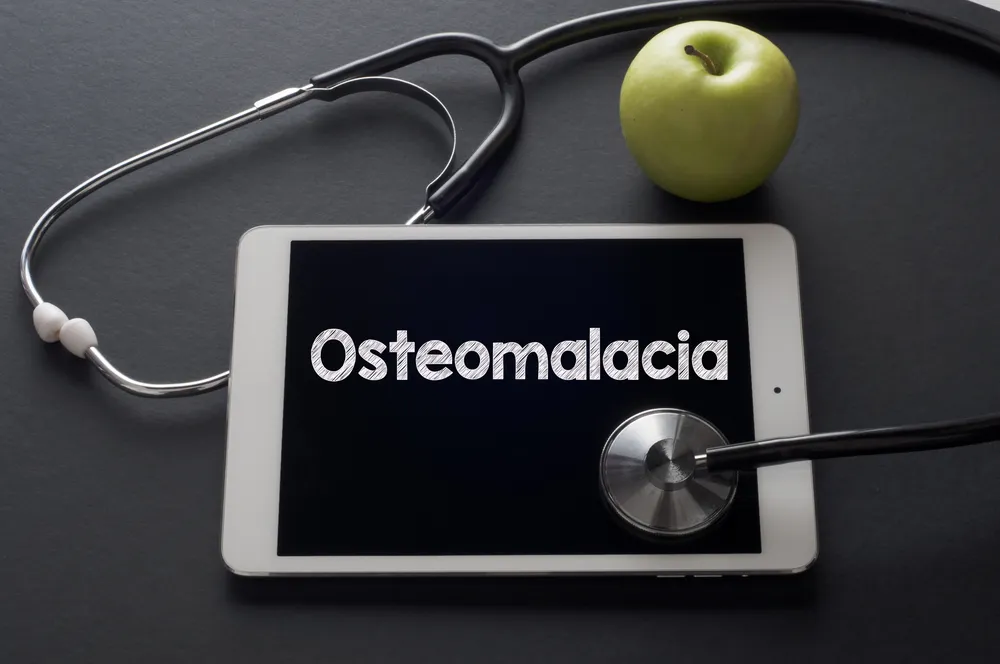
医学用語としては、「首痛(しゅつう)」は主に「しゅつう」と読まれることが多いです。これは他の部位の痛みを表す医学用語と同様のパターンに従っています:
- 頭痛(ずつう)
- 腹痛(ふくつう)
- 胸痛(きょうつう)
- 腰痛(ようつう)
一方、日常会話では「くびいた」と表現することも多く、特に「首が痛い」「首の痛み」といった言い回しで使われます。
医師や医療従事者との会話では「しゅつう」という表現を使うと、より医学的な文脈での会話がスムーズになる可能性があります。ただし、一般的な会話では「くびいた」「首が痛い」といった表現の方が自然に感じられるでしょう。
首痛(しゅつう)の医学的定義とは?
医学的には、「首痛(しゅつう)」は頸部(首の部分)に発生する痛みや不快感を指す用語です。この痛みは、筋肉の緊張、神経の圧迫、骨や関節の問題など、様々な要因によって引き起こされる可能性があります。
首痛は単独で発生することもありますが、頭痛や肩こり、さらには腕や背中の痛みと関連して現れることも多いです。その症状の範囲や強さは、原因となる疾患や状態によって大きく異なることが一般的です。
「首痛」の漢字の意味と由来

「首痛」を構成する漢字それぞれの意味を理解することで、この言葉の本質が見えてきます。
「首」の字の意味
「首」という漢字は、頭と胴体をつなぐ部分、すなわち「首(くび)」を表します。古代中国では、この漢字は人間の頭部を表す象形文字として使われていました。また、「かしら(頭)」「はじめ(始め)」という意味も持ち、物事の最初や重要な部分を示す際にも使用されます。
「痛」の字の意味
「痛」の字は、体の一部に感じる苦痛や不快感を表します。「疒(やまいだれ)」という病気を表す部首と、「甬」(用の古字)という音を表す部分から成り立っています。肉体的な痛みだけでなく、心の痛みや悲しみを表現する際にも使われます。
混同しやすい「首の痛み」に関連する言葉と読み方

「首痛」と似た意味を持つ言葉や、関連する医学用語にはいくつかあります。それぞれの読み方と意味の違いを理解しておきましょう。
| 用語 | 読み方 | 意味・特徴 |
|---|---|---|
| 頚部痛 | けいぶつう | 医学的に首の痛みを指す正式な用語 |
| 首こり | くびこり | 首の筋肉が緊張して硬くなった状態 |
| 頚椎症 | けいついしょう | 首の骨(頚椎)の変形による神経圧迫 |
| 頚肩腕症候群 | けいけんわんしょうこうぐん | 首・肩・腕にかけての痛みやしびれを伴う症状群 |
首痛を感じたときの一般的な原因と注意点

首の痛みを感じる原因は様々です。主な原因としては以下のようなものが考えられます:
筋肉の痛み
最も一般的な首痛の原因は、筋肉の緊張や疲労です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用(いわゆる「スマホ首」)、不適切な姿勢、運動不足などによって引き起こされる傾向があります。
50過ぎたあたりから首こり肩こり背中こり、腰痛も含め、もう体中が痛いぐらいで、毎日ちょっと薬飲んだり湿布張ったりしました。マッサージしてる時だけ気持ちいいですが、終わったらもう全然変わらないんですよね。
骨の痛み
頚椎(首の骨)の変形、椎間板ヘルニア、頚椎症などが原因で痛みを感じる可能性があります。一般的に、これらの症状は加齢や外傷に関連していることが多いとされています。
神経の痛み
頚椎神経根症などの神経が圧迫されることによる痛みが生じることがあります。この場合、首だけでなく肩や腕にかけてのしびれや痛みを感じることがあるとされています。
その他の原因
ストレス、不眠、加齢、不良姿勢などが首痛を悪化させる可能性があります。また、まれに重大な疾患(髄膜炎、腫瘍など)の症状として首痛が現れることもあるため、長期間続く強い痛みや、他の気になる症状がある場合は医療機関を受診することをおすすめします。
首の痛みが強い、長期間続く、または通常の動きで激しい痛みがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。
専門家の見解:首こり・首痛の根本的な解決法
首の痛みやこりに悩む多くの方は、マッサージやストレッチ、シップなどの対症療法に頼りがちですが、これらは一時的な効果しかないことがあります。実は、首の問題は体全体のバランスや他の部位の状態と密接に関連していることが考えられます。
特に注目すべきは、手首や腕の筋肉の状態です。デスクワークやスマホの使用で手首の筋肉が硬くなると、その代わりに腕、肩、そして首の筋肉が過剰に働き、首こりや痛みの原因となる可能性があります。首回りの緊張は自律神経や脳への血流にも影響し、脳疲労や眼精疲労、さらには睡眠の質低下につながることもあるとされています。
このような場合、手首の「サボリ筋」トレーニングが効果的かもしれません。これは手首の筋肉に適切な刺激を与えることで、首や肩の緊張を緩和するアプローチです。根本的な原因にアプローチすることで、長期的な改善が期待できる場合があります。
首痛(しゅつう・くびいた)の改善策

首痛を改善するためには、症状の原因や程度に応じたアプローチが効果的な場合があります。ただし、個人差があるため、専門家に相談することをおすすめします。以下に、一般的な改善策をご紹介します。
安静
痛みが強い場合は、無理に動かさずに安静にしましょう。特に急性の痛みがある場合は、安静が第一です。
冷やす・温める
急性の痛み(特に炎症がある場合)には冷やす、慢性の痛みには温めるという方法が効果的とされています。冷やす場合は氷などを包んでタオルでくるみ、直接肌に当てないようにしましょう。温める場合は、入浴やホットタオル、温熱パッドなどを利用します。
ストレッチ
首の筋肉をゆっくりと伸ばすストレッチは、血行を促進し、緊張を和らげるのに役立つことがあります。ただし、痛みを感じる場合は無理をせず、痛みのない範囲で行いましょう。
マッサージ
首の筋肉をほぐすと、血行が良くなって痛みが和らぐことがあります。自分でできる簡単なマッサージや、プロによるマッサージを検討してみましょう。
姿勢の改善
長時間同じ姿勢でいると、首に負担がかかります。定期的に休憩し、姿勢を正すようにしましょう。特にデスクワークやスマートフォン使用時の姿勢に注意が必要です。
1番は朝の目覚めが痛くなく起きれるようになったことです。車の中でも今までは痛くてゴリゴリやりながら運転してたんですけど、それがセルフケアの後でゴリゴリしなくても運転できるようになりました。あとは首が上に普通に向けるようになったのがすごく嬉しくて。
医療機関への受診
痛みが強い場合や、改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。特に以下のような症状がある場合は早めの受診をおすすめします:
- 激しい痛みや、徐々に悪化する痛み
- 腕や手にしびれや力の低下がある
- 頭痛や吐き気を伴う
- 外傷の後に生じた痛み
- 発熱を伴う痛み
受診する科
- 整形外科:骨や筋肉の痛み、外傷などが疑われる場合は、整形外科を受診することが考えられます。
- 神経内科:神経の痛みや、神経系の病気が疑われる場合は、神経内科を受診することが適切かもしれません。
- その他:必要に応じて、他の科を受診することもできます。
首痛を予防するために

首痛を予防するためには、日常生活での習慣改善が重要です。
正しい姿勢を心がける
スマートフォンやパソコンを使用する際は、正しい姿勢を意識しましょう。長時間の使用は避け、定期的に休憩を取ることが大切です。
適度な運動
運動不足は、筋肉の硬さや血行の悪さを招く可能性があります。適度に運動して、体を動かすようにしましょう。特に首や肩の筋肉を強化するような運動が効果的とされています。
十分な睡眠
睡眠不足は、筋肉の緊張や自律神経の乱れを招く可能性があります。十分な睡眠をとりましょう。また、枕の高さや硬さも首の負担に影響するため、自分に合った枕を選ぶことも大切です。
ストレスを軽減させる
ストレスは、筋肉の緊張や血行の悪さを招く傾向があります。ストレスを軽減させるために、リラックスできる時間を持つようにしましょう。
首痛(しゅつう・くびいた)に関するよくある質問

Q. 「首痛」は「しゅつう」と「くびいた」のどちらが正しいですか?
A. どちらも正しい読み方です。「しゅつう」は音読み、「くびいた」は訓読みで、使用される文脈によって使い分けられます。医学的な文脈では「しゅつう」、日常会話では「くびいた」が用いられることが多いです。
Q. 首痛はどんな症状がありますか?
A. 首痛の症状には、首の痛み、首が動かしにくい、肩や背中への痛み、場合によっては頭痛や吐き気などがあります。症状の種類や強さは原因によって異なります。
Q. 首痛で病院を受診するタイミングはいつですか?
A. 首の痛みが強い、長期間続く、日常生活に支障をきたす、腕や手にしびれや力の低下がある、頭痛や吐き気を伴う、外傷後に生じた、発熱を伴うなどの症状がある場合は、医療機関を受診することをおすすめします。
Q. 首痛とスマートフォンの使用に関連はありますか?
A. はい、関連があります。スマートフォンを見るために首を長時間前に傾けていると、首の筋肉に負担がかかり、「スマホ首」と呼ばれる症状を引き起こすことがあります。定期的に休憩を取り、目線の高さでスマートフォンを持つなどの工夫が必要です。
Q. 首の痛みを自宅で改善する方法はありますか?
A. 軽度の首痛であれば、適切な休息、温冷療法、ゆっくりとしたストレッチ、姿勢の改善などで症状が和らぐことがあります。また、最近では手首のトレーニングが首こりを改善するという考え方もあります。しかし、症状が重い場合や改善が見られない場合は、自己判断せず医療機関を受診してください。
Q. 首痛と肩こりの違いは何ですか?
A. 首痛は主に首の部分に発生する痛みや不快感を指し、肩こりは肩や肩甲骨周辺の筋肉が緊張して硬くなった状態を指します。ただし、これらは互いに関連していることが多く、首の問題が肩こりを引き起こしたり、その逆も起こりうるため、総合的なケアが必要です。
Q. セルフケアで首痛は改善できますか?
A. 適切なセルフケアによって首痛が改善することもあります。ストレッチ、筋力トレーニング、姿勢の改善、温冷療法などが効果的です。特に体全体の筋肉バランスを整えるアプローチが重要で、手首や腕の筋肉のケアも首こりの改善に役立つことがあります。ただし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、専門家の指導を受けることをおすすめします。

