この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。
変形性膝関節症の重症度は、一般的にKL分類というレントゲン画像に基づいて判断される傾向があります。グレードは0から4まであり、グレード2以上で変形性膝関節症と診断される可能性が高いです。この記事では、Kellgren-Lawrence分類の詳細から各ステージの症状、治療法まで専門的に解説します。膝の痛みでお悩みの方や診断を受けた方に、最適な治療選択の参考となる情報をお届けします。
目次
変形性膝関節症とは?基本的な原因と主な症状

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで生じる疾患です。したがって、加齢や肥満、外傷、O脚変形などが主な原因となります。また、多くの患者さんが膝の痛みや機能障害に悩まされており、日本では高齢者の約半数が罹患している可能性があるとされています。
変形性膝関節症の主な原因
変形性膝関節症の発症には、以下のような要因が関係している可能性があります。さらに、これらの要因は相互に影響し合うことが知られています:
- 加齢:軟骨の変性や再生能力の低下が生じる傾向があります
- 肥満:膝関節への負担が増加し、軟骨への圧迫が強くなります
- O脚変形:内側への荷重集中により軟骨摩耗が促進されます
- 外傷:過去のケガや損傷が後の変形性変化につながる可能性があります
- 遺伝的要因:家族歴がある場合、発症リスクが高まる傾向があります
- 女性:閉経後の女性では発症率が高くなることが報告されています
初期から進行期にかけての症状の変化
変形性膝関節症の症状は進行とともに段階的に変化する傾向があります。さらに、初期には軽度の痛みや違和感から始まります。その結果、進行すると日常生活に大きな影響を及ぼすようになる可能性があります。また、症状の現れ方には個人差があることも特徴的です。
健康が一番の財産。理学療法士の笹川です。普段は色々対応しているのですが、今日は変形性膝関節症ですね。熱感がございます。ですから痛いですね。痛いのは内側が痛いんですね。
変形性膝関節症の重症度を判断する「KL分類(グレード分類)」とは?

Kellgren-Lawrence分類(KL分類)は、レントゲン画像を用いて変形性膝関節症の重症度を評価する国際的な診断基準として広く使用されています。したがって、この分類により医師は患者さんの状態を客観的に把握できます。また、適切な治療方針を決定することが可能になります。さらに、世界中の整形外科医がこの基準を用いることで、統一された診断が行われています。
KL分類の5段階グレード詳細解説
| グレード | 重症度 | レントゲン所見 | 典型的症状 | 治療方針 |
|---|---|---|---|---|
| グレード0 | 正常 | 異常所見なし | 無症状 | 予防・経過観察 |
| グレード1 | 疑い | 軽度の骨棘の可能性、関節裂隙狭小化の疑い | 軽度の違和感・こわばり | 運動療法・生活指導 |
| グレード2 | 軽度 | 明確な骨棘、軽度関節裂隙狭小化 | 起床時痛・歩行開始時痛 | 保存療法(運動・薬物) |
| グレード3 | 中等度 | 中等度~多発性骨棘、明確な関節裂隙狭小化 | 歩行時痛・可動域制限・腫脹 | 保存療法強化・注射療法 |
| グレード4 | 重度 | 大きな骨棘、著明な関節裂隙狭小化、軟骨下骨硬化 | 安静時痛・著明な変形・機能障害 | 手術療法検討・人工関節 |
診断における重要性と限界
KL分類は医師が治療方針を決定する際の重要な指標となります。しかし、画像所見と症状の程度は必ずしも一致しない可能性も知られています。したがって、患者さんの症状や生活状況、年齢、活動レベルも総合的に考慮して治療が検討される傾向があります。また、MRI検査や関節鏡検査などの追加検査が必要になる場合もあります。
【重症度別】変形性膝関節症の進行と主な症状の変化

初期段階(グレード1-2)の症状と特徴
初期段階では以下のような症状が現れることが多いです。また、これらの症状は軽度であることが特徴的です。さらに、症状は間欠的に現れ、休息により改善する傾向があります:
- 動作開始時の痛み:起立時や歩行開始時に生じる短時間の痛み
- 階段昇降時の違和感:特に下りで膝に負担を感じる
- 長時間歩行後の痛み:疲労に伴う軽度な痛みや重だるさ
- 朝のこわばり:起床時の関節の動きにくさ(短時間で改善)
- 天候による影響:雨天時や気圧変化時の違和感
進行期(グレード3)の症状と日常生活への影響
病状が進行すると、日常生活により大きな影響が現れる傾向があります。さらに、以下のような症状が特徴的です。その結果、生活の質(QOL)の低下が問題となります:
- 歩行時の持続的な痛み:平地歩行でも痛みが継続する
- 膝の可動域制限:曲げ伸ばしが困難になり、正座ができなくなる
- 階段昇降の困難:手すりなしでの昇降が困難になる
- 膝関節水腫:膝に水がたまり、腫れや重だるさを感じる
- O脚変形の進行:見た目にも変形が明らかになる
- 筋力低下:太ももの筋肉(大腿四頭筋)の萎縮が生じる
末期段階(グレード4)の症状と重篤な機能障害
最も重症な段階では、以下のような状態となる可能性があります。その結果、日常生活が著しく制限されます。また、介護が必要になる場合もあります:
- 安静時痛の出現:座っていても痛みが続く
- 歩行の著しい困難:短距離でも歩行が困難になる
- 膝の著明な変形:O脚やX脚変形が高度になる
- 関節可動域の高度制限:膝の曲げ伸ばしが大幅に制限される
- 歩行補助具の必要性:杖や歩行器が必要になる
膝を伸ばすこともできなくて、曲げることもできなくて。ここへ来院した頃は、もうすでにしゃがむことができない状態で、右の膝が全く曲がらない。90度ぐらいまでしか曲がらないので、しゃがめない状態でした。
変形性膝関節症の検査と診断の詳細な流れ

変形性膝関節症の診断は、段階的な検査によって行われる傾向があります。したがって、正確な重症度の判定のために、複数の検査方法が組み合わせて用いられます。また、整形外科専門医による総合的な評価が重要とされています。さらに、患者さんの症状や生活状況の詳細な聴取も診断に欠かせません。
問診と身体診察
まず医師は詳細な問診を行います。さらに、症状の経過、痛みの性質、日常生活への影響を確認します。その後、膝関節の触診により腫れや圧痛、可動域、安定性を評価する傾向があります。また、歩行状態の観察も重要な診断要素となります。
画像検査の種類と特徴
診断には以下の画像検査が用いられることが多いです。それぞれに特徴があり、診断に重要な情報を提供します:
- レントゲン検査:KL分類による重症度評価の基本となる検査。骨の変化を明確に描出
- MRI検査:軟骨や半月板、靭帯の詳細な状態を確認。早期変化の検出が可能
- 関節鏡検査:必要に応じて関節内の直接観察を行う。治療も同時に実施可能
- 関節造影:関節内の詳細な構造を評価する特殊検査
レントゲン検査は最も重要な検査です。したがって、骨棘の形成や関節裂隙の狭小化、軟骨下骨硬化の程度を評価してKL分類を決定します。また、荷重位での撮影により、実際の関節への負荷状態を評価することが可能です。
重症度に合わせた変形性膝関節症の治療法とは?

変形性膝関節症の治療は、重症度や患者さんの症状、生活状況、年齢に応じて選択される傾向があります。また、大きく分けて保存療法と手術療法があります。さらに、近年は再生医療も注目されており、新たな治療選択肢として期待されています。治療の目標は痛みの軽減、機能改善、生活の質向上です。
保存療法(非手術的治療)の詳細
初期から中等度の変形性膝関節症では、まず保存療法が検討される傾向があります。したがって、以下のような多角的なアプローチが用いられます。また、患者さんの積極的な参加が治療成功の鍵となります:
運動療法とリハビリテーション
運動療法は保存療法の中核を成します。また、以下のような内容が含まれます。さらに、理学療法士による専門的な指導が効果的です:
- 筋力強化訓練:太ももの筋肉(大腿四頭筋)やお尻の筋肉(殿筋群)の強化
- 可動域訓練:関節の柔軟性維持・改善のためのストレッチング
- 有酸素運動:水中歩行、自転車運動などの低負荷有酸素運動
- バランス訓練:転倒予防と関節安定性向上のための訓練
- 日常生活動作訓練:階段昇降、立ち上がりなどの実用的な動作練習
薬物療法の選択肢
症状緩和のために薬物療法が用いられることがあります。また、患者さんの症状や併存疾患に応じて選択されます:
- 内服薬:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、アセトアミノフェンなど
- 外用薬:消炎鎮痛剤の塗り薬、貼り薬
- 関節内注射:ヒアルロン酸注射、ステロイド注射
- トリガーポイント注射:筋肉の緊張緩和を目的とした注射
装具療法と日常生活指導
関節への負担軽減のために装具療法が検討される場合があります。また、日常生活の工夫も重要です:
- 膝関節サポーター:関節の安定性向上と痛み軽減効果
- 足底板:荷重バランス調整による膝への負担軽減
- 杖の使用:歩行時の膝への負担軽減
- 生活環境の改善:手すりの設置、段差の解消など
手術療法の適応と種類
保存療法で効果が得られない場合や、重症度が高い場合には手術療法が検討される可能性があります。したがって、以下のような手術方法があります。また、患者さんの年齢、活動レベル、全身状態を考慮して選択されます:
関節鏡視下手術(内視鏡手術)
関節内の清掃や軟骨の整理を行う低侵襲な手術です。また、比較的軽度から中等度の症例に適応される傾向があります。さらに、入院期間が短く、回復が早いことが特徴です。
高位脛骨骨切り術(HTO)
脛骨を切って角度を調整する手術です。さらに、膝関節への荷重バランスを改善します。その結果、比較的若い患者さんや活動レベルの高い方に適応されることが多いです。また、自分の関節を温存できることが大きなメリットです。
人工関節置換術
重度の変形性膝関節症に対して行われる手術です。したがって、損傷した関節を人工関節に置き換える治療法です。また、全置換術と部分置換術があり、患者さんの状態に応じて選択されます。
- 全人工膝関節置換術(TKA):膝関節全体を人工関節に置換
- 部分人工膝関節置換術(UKA):膝関節の一部のみを人工関節に置換
再生医療の最新動向
近年注目されている治療法として、以下のような再生医療があります。また、これらの治療は新しい選択肢として期待されています。さらに、自分の組織を利用するため、安全性が高いとされています:
- PRP療法:患者さんの血液から血小板を濃縮して関節内に注射
- APS療法:自己タンパク質溶液を用いた関節内注射療法
- 培養幹細胞治療:患者さんの幹細胞を培養して関節内に移植
- 培養軟骨移植:患者さんの軟骨細胞を培養して移植する治療
専門家の見解:症状改善への取り組みと実際の治療効果
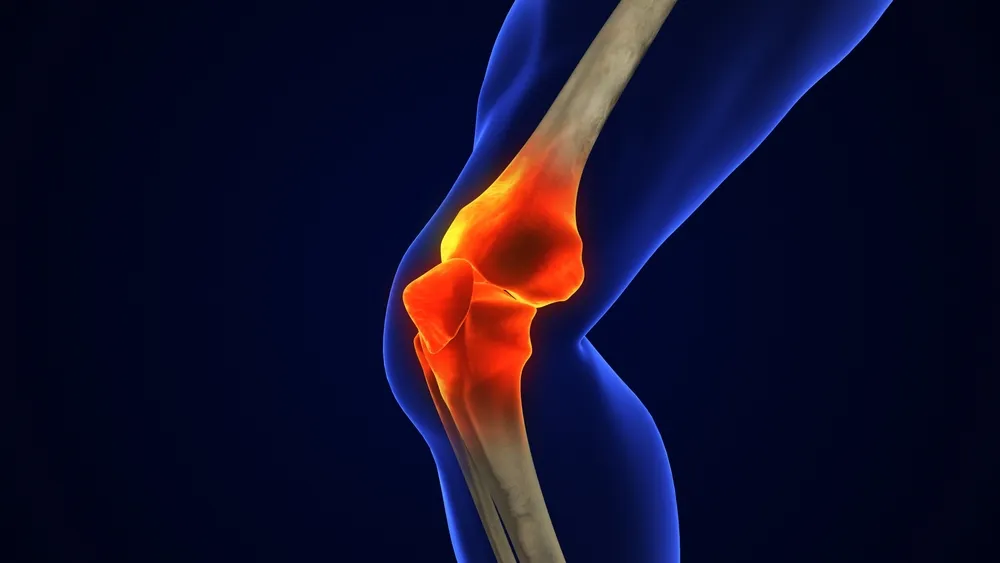
実際の治療現場では、画像診断だけでなく患者さんの症状や生活状況を総合的に評価することが重要です。また、継続的な治療とセルフケアが症状改善の鍵となります。さらに、患者さんの治療に対するモチベーションや理解度も治療効果に大きく影響します。
6回通ってみて、まず自分ではそんなに気が付いてなかったんですけど、先生の方から「かなり筋力付いてます、力強くなってます」と言われて。確かに歩くのも波はあるんですけども、膝の状態によって。でも、確かに1回目の時よりは全然楽になっていて、6回目終わった頃には、スタスタと歩けるようになりました。
この事例からも分かるように、適切な治療とセルフケアの継続により、症状の改善が期待できる可能性が示されています。したがって、重要なのは患者さん自身が治療に積極的に取り組むことです。また、定期的な経過観察と治療内容の調整も必要となります。
日常生活での注意点と効果的な予防法

変形性膝関節症の進行を防ぐためには、日常生活での注意が必要です。また、以下のような予防策が効果的とされています。さらに、早期からの予防的取り組みが重要です:
生活習慣の改善
- 体重管理:膝関節への負担を軽減する効果が期待できます。1kg減量で膝への負担は3-4kg軽減
- 適度な運動:筋力維持と関節可動域の保持に役立つ可能性があります
- 正しい姿勢:膝への負担を分散する効果があります
- 禁煙:血流改善により軟骨の栄養状態向上が期待できます
日常動作の工夫
- 靴選び:クッション性の良い靴の着用が推奨されます
- 階段の昇降:手すりを使用し、ゆっくりと行います
- 重い物の持ち運び:膝への負担を考慮し、カートなどを活用
- 座り方の工夫:正座を避け、椅子生活を心がけます
セルフケアと予防運動
- 温熱療法:入浴や温湿布による血行促進と痛みの軽減効果
- ストレッチング:関節可動域維持のための定期的なストレッチ
- 筋力維持運動:太ももの筋肉を中心とした筋力トレーニング
- マッサージ:周囲の筋肉の緊張緩和
詳しい医学的根拠については日本整形外科学会や厚生労働省関節疾患情報をご参照ください。
変形性膝関節症の重症度に関するよくある質問

Q. 変形性膝関節症の重症度はどのように判断されますか?
A. 変形性膝関節症の重症度は、主にKellgren-Lawrence分類(KL分類)というレントゲン画像による評価基準で判断される傾向があります。グレード0から4までの5段階で分類され、グレード2以上で変形性膝関節症と診断される可能性が高いです。診断には患者さんの症状や身体所見も総合的に考慮されます。
Q. KL分類のグレード4とはどのような状態ですか?
A. KL分類のグレード4は最も重症な状態で、関節の隙間がほとんどなくなり、大きな骨棘が形成されている可能性があります。軟骨下骨の硬化も著明に認められます。この段階では安静時痛や著明な機能障害が生じるため、手術療法の検討が必要になる場合があります。
Q. 重症度が高くても症状が軽い場合はありますか?
A. はい、その可能性があります。変形性膝関節症では、KL分類で重症度が高くても症状が軽度な場合や、逆に重症度が低くても強い症状を示す場合があります。画像所見と症状の程度は必ずしも一致しない傾向があります。これは軟骨には神経がないため、痛みは周囲の組織の炎症や筋肉の緊張によることが多いためです。
Q. グレード2の変形性膝関節症はどのような治療が行われますか?
A. グレード2では主に保存療法が選択される傾向があります。運動療法(筋力強化、ストレッチング)、薬物療法(消炎鎮痛薬、ヒアルロン酸注射)、装具療法(サポーター、足底板)、生活指導などを組み合わせて症状の改善を図ることが一般的です。患者さんの症状や生活状況に応じて治療内容が調整されます。
Q. 人工関節手術はどのような場合に検討されますか?
A. 主にグレード4の重度の変形性膝関節症で、保存療法で効果が得られず、日常生活に著しい支障をきたしている場合に検討される可能性があります。患者さんの年齢、活動レベル、全身状態、社会的背景なども考慮して決定される傾向があります。また、患者さんの治療に対する希望や理解も重要な要素となります。
Q. 変形性膝関節症の進行を遅らせることはできますか?
A. はい、可能性があります。適切な運動療法、体重管理、生活習慣の改善により進行を遅らせることが期待できます。特に筋力強化と関節可動域の維持、適正体重の維持が重要とされています。早期の診断と治療開始、定期的な経過観察が進行予防に効果的です。
Q. MRI検査は必要ですか?
A. レントゲン検査で診断が困難な場合や、軟骨や半月板、靭帯の詳細な状態を確認したい場合にMRI検査が行われることがあります。KL分類はレントゲン検査で判定されますが、治療方針の決定にMRI情報が役立つ可能性があります。特に早期の軟骨変化の検出や手術適応の判断に有用です。
まとめ:重症度を理解し、適切な治療選択へ

変形性膝関節症の重症度は、KL分類によるレントゲン評価が基本となりますが、患者さんの症状や生活状況を総合的に考慮して治療方針を決定することが最も重要とされています。
早期発見・早期治療により、症状の進行を遅らせることが可能です。したがって、膝の痛みや違和感を感じたら、整形外科専門医に相談することをお勧めします。また、適切な診断と個別化された治療により、多くの患者さんが生活の質の改善を実感されています。
さらに、日常生活での予防対策も重要です。適度な運動、体重管理、正しい姿勢を心がけることで、膝関節の健康を維持できる可能性があります。その結果、医師と相談しながらあなたに最適な治療法を見つけていくことが、症状改善と生活の質向上への近道となります。
変形性膝関節症は進行性の疾患ですが、適切な治療と継続的なセルフケアにより、症状をコントロールし、活動的な生活を維持することが期待できます。また、新しい治療法や再生医療の発展により、今後さらなる治療選択肢の拡大が見込まれています。
関連記事

